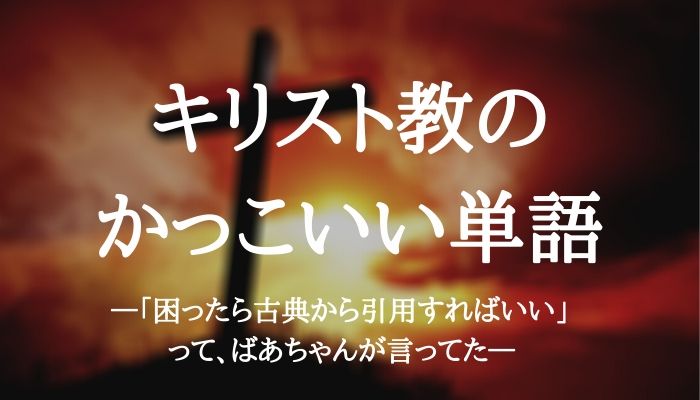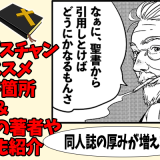Twitterにいる聖書に詳しいみなさん(おもにキリスト教徒の方々)のお力添えを得て、「キリスト教のかっこいい単語」あつめてみました。
呼びかけた私どもがプロテスタントなのでプロテスタント成分多めになっておりますが、カトリックの方や正教会にくわしい方などからもご意見いただいてます。みなさまの参考になれば幸いです!
→キリスト教用語集(日本キリスト教団 西神戸教会)
※ツイートが増えてきたので、50音順+カンタンな解説を現在整理中です。お見苦しいところがあったら申し訳ありません。※
▼こちらもよければ
目次
基本的には「ギリシャ語」「ラテン語」を探せばいい説 is ある
キリスト教というのは、ヘブライ語の聖書であるタナッハに基づいたユダヤ教を再解釈するするさいに「翻訳」という行為を神学的に肯定し、『意味の宗教』であることによって全世界に拡散することができた宗教、だと思います。
その最初のほうに翻訳されたのがギリシャ語だったりラテン語だったりするわけです。
現代日本という文化圏に生きるわれわれからしてみたら、ギリシャ語もラテン語も「キリスト教(あるいは『聖書』)」という接点がなければ触れることがないようなもの――逆を言うと、われわれのようなギリシャ語にもラテン語にも接点がなくて済む文化圏に生きる者は「キリスト教 (あるいは『聖書』) 」との接触なしにギリシャ語やラテン語に触れる必然性があんまりない…
(と言うとウェルギリウスの叙事詩とかプラトンとか原典で読むぜ派の方からブーイング出るかもしれませんが…言わせてもらうと、それはかなり少数派であると思いますのでここでは考慮せずにしゃべります)
何が言いたいのかと言うと、

ギリシャ語とかラテン語とか探すと、キリスト教にゆえんのあるそれっぽいかっこいい横文字を勝手に抽出することができるのでは?
ということです。「こんなぺージだけじゃ足りねぇ、もっと幅広く探したい」という方の参考になれば幸いです。以下、私が読んでいて「これ耳慣れないかっこいい言葉多すぎィ!」と思った古代教父『エウゼビオス』の著作も紹介します。参考になれば幸いです。
あいうえお
I AM THAT I AM(「私は在る」という者である)
明けの明星
当コラムライターが好きな響きなのでピックアップ。
夜明けの前に東の空に美しく輝いて見える金星を指す.太陽系の第2惑星で,地球のすぐ内側の起動を回っており,古くから「明けの明星」として親しまれている.
ヨブ38:7では神が天地を創造された際,「明けの明星の星々が共に喜び歌った」と表現されている.ヨブはその苦しみの中で自分の生れた日を呪い、「夜明けの星が暗くなれ」(ヨブ3:9)と表現している.イザ14:12では悪政を行うバビロン王を象徴するものとして引用されている.Ⅱペテ1:19ではキリストの再臨を指して引用されている.また黙示録2:28では最後までキリストに従う者たちへ報いとして明けの明星が与えられること,22:16ではキリスト御自身が「輝く明けの明星」と表現されている.
(「新聖書辞典」いのちことば社,1985年p.15)
アクシオス
アクシオス(ギリシア語: ἄξιος)は元々はギリシャ語で「価値が有る」「ふさわしい」「値する」の意。新約聖書にも複数個所に使われている[3]。正教会では新たに聖職者が叙聖される時に使われる事から「適任」という訳が当てられることもある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
聖体礼儀で行われる神品機密に際し、新しく叙聖された者(主教もしくは司祭もしくは輔祭に新たに叙聖された者)に対して祭服等が与えられる度に「アクシオス」と三回ずつ歌われる。会衆(詠隊)が「アクシオス」と3回歌うのは、叙聖に対する同意を示している。神品機密・叙聖の時のみならず、昇叙や、なんらかの名誉の授与といった場面でも唱えられ、歌われる。また、新たに聖人が列聖されたことを知らせる際等に、「(聖人に)ふさわしい」との同意を込めて「アクシオス!」と書かれる事がある。
アドベント
アドベント (Advent) は、キリスト教西方教会において、イエス・キリストの降誕を待ち望む期間のことである。日本語では待降節(たいこうせつ)、降臨節(こうりんせつ)、または待誕節(たいたんせつ)という。教派によって名称が異なり、主にカトリックや福音主義教会(ルター派)では待降節、聖公会では降臨節と呼ぶ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アドナイ
ユダヤ・キリスト・イスラムでの唯一神YHVHの名前の一つ。
参考:ピクシブ百科事典
アドンに対してアドナイはその複数形、または「我が主」を意味するとされ、神と人間の関係を如実に現す名とも解釈される。モーセの十戒で『神の名前』を直接用いることが禁止されたため、「アドナイ」で代用した結果、本当の神の名の発音が散逸してしまったという経緯が存在する。
アナフェマ(アナテマ)
アナテマ(ανάθεμα, anathema)は、「聖絶」「奉納」「滅ぼす」「捧げる」「殺す」「呪われる」「呪われたものとなる」などと訳されるギリシア語の言葉。聖書で、ヘブライ語「ヘーレム herem」の訳として七十人訳聖書から使われた。アナフェマとも。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アポカリプス
アポカリプス(Apocalypse)とは、キリスト教における『黙示』を表す単語である。
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B9
新約聖書の「ヨハネの黙示録」のギリシャ語原題が「Αποκάλυψις Ιωάννου」(アポカリプシス・イオアノ)であり、ここに由来する。「Ιωάννου」(イオアノ)は要するにヨハネなので、「Αποκάλυψις」(アポカリプシス)が「黙示」あるいは「黙示録」にあたる。
この「Αποκάλυψις」(アポカリプシス)はギリシャ語で「覆いを取る」「開示する」「暴露する」ことを意味した単語だった。現在の「黙示」や「アポカリプス」という言葉にも、「隠されていた真理・知識を神が人々に開示して伝える」という意味は残っている。
だがそれだけではなく、「ヨハネの黙示録」が終末論的な内容であったために、「アポカリプス」や「黙示録」という言葉には「最後の審判」「人類の滅亡」と言ったような終末論的なニュアンスが含まれている。
例えば「ポストアポカリプス」という言葉を例にとると、「~の後」という意味の「ポスト」を「アポカリプス」と合わせた言葉であるから、「知識が伝えられた後」「真理が開示された後」という意味合いを持ちそうな言葉である。しかし「ポストアポカリプス」は実際には「人類文明崩壊後の」と言った意味合いの言葉である。
archange(アルハンゲル大天使)
archangel名〔ユダヤ・キリスト・イスラム教の〕大天使◆ヘブライ聖書(旧約聖書)に大天使の記述はなく、新約聖書でもユダの手紙に「大天使ミカエル」が、またテサロニケの使徒への手紙に「大天使の声」の記述があるだけである。ユダヤ教では少なくとも7人が、キリスト教では伝統的にミカエル(Michael)、ガブリエル(Gabriel)、ラファエル(Raphael)の3人が大天使とされる(4番目にユリエル(Uriel)が来る場合もある)。東方教会では7人が、またプロテスタントでは聖書の記述に従いミカエルのみを大天使とする場合がある。イスラム教ではムハンマドにコーランと伝えたとされるジブリール、ミーカイール、およびコーランに記述のない「死の天使」のイスラーフィル、イズラーイールが大天使とされる。
(引用:英辞郎On The WEB)
アルハンゲリスキイとは「アルハンゲルの」を意味する語であり、正教会では天使首(「天使のかしら」の意)と訳される。他教派では大天使とも。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アルファでありオメガ
ΑΩ(アルファオメガ)は、新約聖書に現れる語句である。厳密に言えば聖書にこの形では現れてはいないが、しばしば「ΑΩ」もしくは、「アルファとオメガ」に相当する各国語(たとえば、ラテン語: Alpha et Omega、英語: Alpha and Omega)として言及される。新約聖書の「ヨハネの黙示録」(1章8節、21章6節、22章13節) に、主の言葉「私はアルファであり、オメガである」(コイネーギリシャ語: τὸ α καὶ τὸ ω; 英語: I am the Alpha and the Omega)として現れる。なお、21:6 と 22:13 ではこのフレーズの後に「最初であり、最後である」と続く。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
イミタチオ・クリスティ
『キリストに倣いて』(キリストにならいて、De imitatione Christi)は、トマス・ア・ケンピスによって書かれた本である。「第二の福音書」「中世の最高の信心書」とも言われ、聖書に次いでカトリックのクリスチャンの霊的修練の書として識字階級に広く読まれ、親しまれている。修道者が修道者のために書いた本であるが、一般の修得書でもある[1]。
響きがかっこいい。
日本では戦国時代のキリシタンたちも読んでいた信仰書。現在私は天草四郎がこれを読んでいたのかどうか探ってる。
「オペラ座の怪人」(ガストン・ルルー)にて、ヒロインであるクリスティーヌ・ダーエがこれを読んでいたような描写が第三者視点の地の文でも語られている。
エヴァンゲリオン
ギリシア語の euaggelionは元来「よい音信」そのものであれ,「よい音信をもたらす者への報酬」であれ,euaggelos「よい音信をもたらす者」に関する事すべてをさす。宗教的用語としては神秘宗教における神託,皇帝崇拝における皇帝に関する告知をさす。しかし,新約聖書の用語は,始りつつある救いの時の告知を示す旧約聖書の用語に由来し,イエス・キリストによって始る終末的救いの喜ばしい知らせを意味する。のちにこの語はイエスの教えと生涯を記録した書に対して適用されるようになった。
出展:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説(コトバンク)
かきくけこ
偽典(プシュード・エピグラファ)
みんなこういう響き好きなんでしょ。
主として前 200年より 150年までの期間に,権威を高めるために実際の著者以外の名を用いて著わされた諸文書のうち,旧約聖書正典 Canonおよび経典外聖書 (経外典ともいう) Apocryphaに含まれていないもの。『アリステアスの手紙』『ヨベルの書』『イザヤの殉教と昇天』『ソロモンの詩編』『第3,第4マカベア書』『シビルの神託』『第1,第2エノク書』『モーセの昇天』『バルクの黙示録』 (2種) ,『十二族長の遺言』など。ただしカトリック教会では,プロテスタントのいう外典も第2正典として正典に含めているので,プロテスタントのいう偽典は経外典 (外典) と呼ばれている。
グノーシス
みんなこういう響き好きなんでしょ。
グノーシス主義(英: Gnosticism、古代ギリシア語: γνωστικός、ローマ字表記(英語版): gnōstikós、コイネー・ギリシャ語: [ɣnostiˈkos](英語版)、「知識を持つ」の意)は、1世紀後半にユダヤ教と初代教会の諸派の間で融合した宗教的思想と体系の集合である。これらの様々なグループは、宗教機関の原始正統派(英語版)の教え、伝統、権威よりも、個人的な精神的知識(グノーシス(英語版))を重視した。
(ウィキペディア「グノーシス主義」項目 2025年3月30日最終更新)
さしすせそ
死海文書
みんなこういう響き好きなんでしょ。
死海文書には、エステル記を除くヘブライ語聖書のすべての写本が含まれている。いずれも、ユダヤ教の信仰にとってきわめて重要な文書だ。また、キリスト教がユダヤ教から派生したことを考えれば、キリスト教の誕生について紐解く鍵とも言えるかもしれない。
ジェリコの壁(エリコの壁)
エリコの壁(エリコのかべ)は、ヘブライ聖書に書かれているエリコ(イェリコ)の街の城壁である。ウォールズ・オブ・ジェリコ (Walls of Jericho) とも呼ばれる。モーセの後継者ヨシュアはエリコの街を占領しようとしたが、エリコの人々は城門を堅く閉ざし、誰も出入りすることができなかった。しかし、主の言葉に従い、イスラエルの民が契約の箱を担いで7日間城壁の周りを廻り、角笛を吹くと、その巨大なエリコの城壁が崩れた(『ヨシュア記』6章)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
スプララプサリアニズム(Supralapsarianism)
→https://www.imcj.org/watanabe/15B.html
→https://www.imcj.org/watanabe/14B.html
ソドム
たちつてと
罪喰い人
イギリス・ウェールズ南部の民間習俗の話。聖書には別に出てこない響き。かっこよかったのでつい…
ウェールズ南部では人が亡くなると、その小教区の「罪喰い人」を呼ぶ。罪喰い人は、塩のいっぱい入った皿を故人の胸の上に置き、塩の上に一切れのパンを載せる。それからパンに向かって何事かを囁き、それを食べると、早々に家を立ち去る。故人のすべての罪をその人が食べたのだ、と信じられている。罪喰い人はそうやって飲み込んだすべての罪を自分が引き受けるので、罪人とみなされ、一般的に人々から蔑まれている。(Archaeologia Cambrensin,t.Ⅲ,1852,p.330-331: cf. Revue des traditions populaires,t.Ⅵ,p.484)
(引用:「ブルターニュ死の伝承」アナトール・ル=ブラーズ著 後藤澪子訳 p.670)
テオロギア・ネガティーヴァ(存在しない神)
神の本質は人間が思惟しうるいかなる概念にも当てはまらない、すなわち一切の述語を超えたものであるとして、「神は~でない」と否定表現でのみ神を語ろうと試みる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%A6%E5%AE%9A%E7%A5%9E%E5%AD%A6
思想史・哲学史や宗教史の分野では、この「否定神学」の議論一般を伝統的に「テオロギア・ネガティーヴァ」(ラテン語)と呼ぶ。「否定神学」というのはこれの直訳である。(参考:筒井賢治「グノーシス 古代キリスト教の〈異端思想〉」p.92より)
デュオリス
伝道者の書
『コヘレトの言葉』(コヘレトのことば、ヘブライ語:קֹהֶלֶת)、あるいは『コヘレトの巻物』(מְגִילָת קֹהֶלֶת)または『コーヘレト書』は旧約聖書の一文献で、ハメシュ・メギロット(五つの巻物)の範疇に含まれている。ハメシュ・メギロットとは旧約聖書の諸書に属する五つの書物、『コヘレトの言葉』、『雅歌』、『哀歌』、『ルツ記』、『エステル記』を指すユダヤ教の概念である。コヘレトとは「集める者」を意味するので、正しくは『伝道の書』と呼ばれる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
トランサブスタンシエーション(transubstantiation)/聖変化
聖変化(せいへんか、ラテン語: transsubstantiatio、英: transubstantiation、露: Пресуществление)は、カトリック教会のミサや正教会の聖体礼儀において、パンとぶどう酒がイエス・キリストの体(聖体・聖体血)に変化すること。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
なにぬねの
ナグ・ハマディ文書
みんなこういう響の好きなんでしょ。
ナグ・ハマディ写本(ナグ・ハマディしゃほん、The Nag Hammadi Codices)あるいはナグ・ハマディ文書(ナグ・ハマディもんじょ、ぶんしょ、The Nag Hammadi library)とは1945年に上エジプト・ケナ県のナグ・ハマディ(エジプト・アラビア語版)(より正確には、ナグゥ・アル=ハムマーディ[1])村の近くで見つかった初期キリスト教文書のことである。ナグ・ハマディ写本は、二十世紀最大の考古学的発見に数えられており[2]、事実、初期キリスト教の研究を飛躍的に進展させた[2]。ナグ・ハマディ写本は、古代キリスト教を知るための原資料としては死海写本につぐ重要性を持つと見なされている[2]。
ネブカデネザル
聖書では人名として焼く100回近く言及。響きが強そう。
バビロニヤ語で、「(神)ネボは相続権を放棄した」という意味であると思われる。新バビロニヤ(カルデヤ王朝)の創立者ナボポラッサルの子.父の後を継いで帝国最大の王となり、前605年から562年まで帝国を治めた.エレミヤ書やエゼキエル書ではネブカデレザルと呼ばれているが、この型が本来の形に近い音写である.ネブカデネザルの方はおそらくアラム語の形に由来する。
(934
ノアの箱舟(Noah’s Ark)
はひふへほ
パトリアルフ
バプテスマ(バプテスマのヨハネ)
バプテスマ(ギリシア語: βάπτισμα baptisma)とは、キリスト教の礼典の一つである洗礼のことで、バプテスト教会を含むプロテスタントが用いる日本語訳聖書における訳語である
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
洗礼者ヨハネは、『新約聖書』に登場する古代ユダヤの宗教家・預言者。個人の回心を訴え、ヨルダン川でイエスらに洗礼(バプテスマ)を授けた。『新約聖書』の「ルカによる福音書」によれば、父は祭司ザカリア、母はエリサベト。バプテスマのヨハネ、洗者ヨハネとも表記・呼称される。正教会ではキリストの道を備えるものという意味の前駆(Forerunner)の称をもってしばしば呼び、日本ハリストス正教会での呼称は前駆授洗イオアン(ぜんくじゅせんイオアン)。イエスの弟子である使徒ヨハネとは同名の別人である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
イエスの弟子である使徒ヨハネとは同名の別人である。
バビロン(大淫婦バビロン)
聖書では、その名は「バベル」として登場する。創世記では、「混乱する」を意味するヘブライ語の動詞ビルベル(bilbél)から、「混乱」という意味で説明されている]。現代の英語の単語「babble」(意味の無いことを話す)は、一般にはバベルという名前に由来すると考えられているが、直接の関係は無い。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
また、イラクにおけるユダヤ人コミュニティーの起源ともなったが、このようにユダヤ教の成立過程に深く関わったバビロンはユダヤ教やその系譜を引くキリスト教において正義の対抗概念のイメージであり、さらにイザヤ書とエレミヤ書の預言と新約聖書のヨハネの黙示録(ヨハネへの啓示、啓示の書)の故事から、ヨーロッパなどのキリスト教文化圏においては、退廃した都市の象徴(大淫婦バビロン、大娼婦バビロン)、さらには、富と悪徳で栄える資本主義、偶像崇拝の象徴として扱われることが多い。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ハリストス復活、実に復活!(ハリストゥース アネスティ!)
ハリストス復活(ハリストスふっかつ)とは、正教会の復活大祭期間中の挨拶。日本正教会による訳語。イイスス・ハリストス(イエス・キリストの現代ギリシャ語・スラヴ語・ルーマニア語等における発音・転写)の復活を信徒同士で共に記憶する挨拶である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「ハリストス復活!」と信徒の一方が挨拶すると、信徒のもう一方が「実に復活!」(じつにふっかつ!)と答える。復活大祭(パスハ)の奉神礼では主教・司祭と信徒の間で繰り返し用いられると共に、復活祭期の間は信徒の間でこの挨拶が用いられる。その場に参祷している多くの外国人信徒の為に、教会が所在する地域の言語以外の言語で呼びかけ・応答が行われる事もある。
ハヤトロギア
【有賀鉄太郎】より…主著《オリゲネス研究》(1943),《キリスト教思想における存在論の問題》(1969)。キリスト教思想における存在論(オントロギア)をヘブライ思想にさかのぼって論じ,ヘブライ語のハーヤー(存在と生成を含む動詞)にもとづき〈ハヤトロギア〉と規定した。【木田 献一】。…
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%82%A2-1394611
ハヤ・オントロギア
さらに言えば、手島の論考は、京都大学キリスト教学の学統(波多野精一、有賀鉄太郎ら)における「ハヤ・オントロギア」のユダヤ文献学からの言い換えとも見える。「ハヤ・オントロギア」とは、ヘブライ思想とギリシア思想が衝突・対流した、ユダヤ・キリスト教の歴史的核の動態である。
聖書を聖書によって読むこと
パントクラトール(ツェバーオート)=全能者
全能者ハリストスは、イイスス・ハリストス(イエス・キリストのギリシャ語読みに由来する、日本正教会で用いられる転写)のイコンにおける主要な形式であり、ハリストスが天上の王であり審判者である事を示しているものである。デイシスの一部から発展した形式である。ギリシャ語からそのままパントクラトールと転写される事もある。ロシア語では”Спас Вседержитель”(救世主全能者)とも呼ばれる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
主に正教会で用いられるが、ビザンティン美術の影響を受けた西方教会においても用いられない訳ではない。
プロフェティック・パーフェクティブ
フィラデルフィア
7つの教会は、初期キリスト教における7つの主要教会として、新約聖書ヨハネの黙示録で言及されている教会。「黙示の7つの教会」や「アジアの7つの教会」としても知られている(この場合の「アジア」とはローマ時代のアジアであって、現代で言うところの小アジアすなわちトルコのアナトリア半島を指す)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「ヨハネの黙示録」では、古代ギリシャの島であるパトモスで、イエス・キリストが弟子のパトモスのヨハネに福音を通して次のように伝えたとされる。「あなたが見たものを巻物に書きなさい。そして7つの教会に送りなさい。エフェソス、スミルナ、ペルガマ、ティアティラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオディキア」。
ボアネルゲ(雷の子)
まみむめも
Messiah(メシア・メサイア)
メシアは、ヘブライ語のマシアハ(משיח)に由来し、「(油を)塗られた者」の意。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
出エジプト記には祭司が、サムエル記下には王が、その就任の際に油を塗られたことが書かれている。後にそれは理想的な統治をする為政者を意味するようになり、さらに神的な救済者を指すようになった。
メシアのギリシャ語訳がクリストス(Χριστός)で、「キリスト」はその日本語的表記である。キリスト教徒はナザレのイエスがそのメシアであると考えている。イエスをメシアとして認めた場合の呼称がイエス・キリストである。イスラム教徒もイエスをメシア(マスィーフ)と呼ぶが、キリスト教とは捉え方が異なっている。
ヘブライ語マシアハがギリシャ語にはいってメシアス(μεσσίας)となった。日本語のメシアはメシアスに由来する。メサイアは同じ語に由来する英語。
メタノイア(悔い改め)
聖書ギリシア語「メタノイア(μετάνοια – matanoia)」の意味に関して、本田哲郎神父はその著書『聖書を発見する』(岩波書店)の中で、独特の見解を披露しています。
(引用:Josephology「七十人訳聖書のメタノイア」)
・「これはマルコ福音書の中で、最初にイエスが口を開く場面です。何を言ったのだろうかと、興味深い箇所です。『時は満ち、神の国はすぐそこに来ている。低みに立って見直し、福音に信頼してあゆみを起こせ』。わたしたちの耳に慣れているのは、『時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい』という翻訳かもしれません。」(27ページ)
やゆよ
ヨハネ
「ヨハネ」ってかっこよくないですか。
〔ヘブライ語〕ヨーハーナーンのギリシア語刑で、「主は恵み深い」という意味.
聖書には「ヨハネ」という名の人物が少なくとも5人は出てくるので注意~。
「聖ヨハネの日」は夏至。冬至たるクリスマスと対をなす日。
ヨベルの年
なんかカッコよくないですか?
第7の安息年(7年ごと)
(中略)
[ヘブライ語]ヨーベールは喜びの響き,ラッパの響きを意味している。第7月10日の贖いの日に角笛を響かせて喜びを告知したことからヨベルと呼ばれた.売られた土地は元の所有者に返され、奴隷は自由の身となる.(いのちのことば社「新キリスト教辞典」1992年,p.1210)
らりるれろ
レビヤタン(レヴィアタン・リヴァイアサン)
レヴィアタン(ヘブライ語: לִוְיָתָן Livyatan, 発音: リヴヤタン, ラテン語: Leviathan, 英語発音: [liˈvaiəθən] リヴァイアサン, 日本語慣用表記: レビヤタン)は、旧約聖書に登場する海中の怪物(怪獣)。悪魔と見られることもある。「ねじれた」「渦を巻いた」という意味のヘブライ語が語源。原義から転じて、単に大きな怪物や生き物を意味する言葉でもある。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ロゴス・スペルマティコス
ここには「哲学は神学の侍女」([ラテン語]philosophia ancilla theologiae)の合言葉とは逆に,聖言啓示なしに理解された哲学的な神,人間,世界についての自然的理解が根本にあるので,実質的には,自然的理性の全領域支配,理性の自律性の全領域における承認がある.ここでは,理性と信仰の問題は「自然的理性の秩序と信仰の秩序の総合」,端的には「自然的理性と信仰の総合」と考えられている.この場合,恩恵の注入を受けない非キリスト者と注入を受けたキリスト者の真理理解の相違は,理解の完全性の程度の問題であり,認識的倫理的に両者の間に広大な共通領域が存在することになる.<復> この立場は,教父の立場に類型を求めると,ユスティノスからアレキサンドリア教校を経てスコラ哲学につながる線上でとらえることができる.ユスティノスにはロゴスの種子([ギリシャ語]ロゴス・スペルマティコス)の思想があり,ギリシヤ哲学者にもロゴスの不完全ではあるが認識的に正当な顕現を認める.旧約の預言者と新約との関係と相等しい関係がギリシヤ哲学者と新約との間にあり,「理性と信仰が未完成と完成の関係で考えられている」(山中良知).
https://www.wordoflife.jp/bible-1063/
ロマムティ・エゼル
ヘブライ語による人名。
「先見者」という意味.神殿楽人の一人.コラの子孫へマンの子でケハテ族(Ⅰ歴代誌25:4,).
(いのちのことば社「新聖書辞典」1985年,p.1420)
わをん
…未整理…
 聖書からの名言引用は悪手?代わりにキリスト教世界観作家とか哲学者たちをまとめる~力尽きた、ここからたぐって~
聖書からの名言引用は悪手?代わりにキリスト教世界観作家とか哲学者たちをまとめる~力尽きた、ここからたぐって~
 「ヨハネの黙示録の名言」?構成、解釈の種類、他書簡との比較も紹介【同人誌をアツくする聖書入門】
「ヨハネの黙示録の名言」?構成、解釈の種類、他書簡との比較も紹介【同人誌をアツくする聖書入門】
 「聖書は作り話か」とか「カインとアベルの話、神が悪い」「ユダは本当に裏切り者だったのか」とかの真実を知るには
「聖書は作り話か」とか「カインとアベルの話、神が悪い」「ユダは本当に裏切り者だったのか」とかの真実を知るには
 【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】
【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】

聖書の物語論的読み方―新たな解釈へのアプローチ