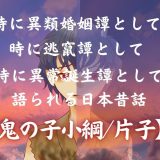「ユダヤ民話40選」を読んでいて、思わず立ち上がってしまった話があるので紹介してみます。
ユダヤ民話「王女に口をきかせた若者の話」あらすじ
ある国の国王は、自分の娘が美しいことを誇りに思っており「王女に、見事口をきかせることができた者は、王女を妻にし。王の息子となる」というおふれを出していた。これまで97名の挑戦者がいたが、いずれも失敗し、首を斬り落とされ、とがった棒に突き刺されて、宮殿の壁の上にさらしものにされていた。
この国のある町に年老いた夫婦が三人息子と暮らしていた。老夫婦の夫が死ぬと、よからぬ者たちが「お前たちの父はわしらに借金があった」と言って財産を持って行ってしまう。
この状況に嘆き悲しみを覚えた長男は「運を見つけに他の町へ行く」と言って都に行き、例の王女のおふれを知る。長男は運試しに挑戦するが、あえなく敗れ、98番目のさらし首となる。
長男が出て行ったことを嘆き続けている母親に嫌気がさした次男も家を出ていく。都にやってきた次男は兄が晒し首にされているのを見て嘆くが、自分も運試しに王女に挑戦する。が、これもまた失敗し、99番目のさらし首となる。
一番下の末息子は兄弟の中でもたいそうな豪傑だった。ある日、長男と次男を探しに行くと告げて家を出て、都で兄二人ともがさらし首になっているのを見つける。
事の次第(王女の挑戦)を知った末息子は、一度
アラブ人のコーヒーショップに入り、落ち着かない様子だったが、自分も王女に挑戦することを決めて宮殿の門前に立った。
身支度して王女の部屋に連れてこられた青年は、部屋に入っても挨拶もせずだまりこくっていた。一つのベッドには王女が座り、もう一方のベッドは末息子が占領し、そうしているうちに末息子はポケットから一台の燭台を取り出し、燭台相手にしゃべり始める。
それを見た王女は「お前、何をしているの?気でも狂っているの?燭台と話をしているの?」「燭台と話しているなんて、お前、気違いだわ、きっとそうよ!」と言葉を発し、それを番兵たちも聞いていたので、王女は末息子の所有物として認められることとなる。
朝になると宰相がやってきて、王女の挑戦の成功者が出たことを知る。この宰相はかねてより自分の息子と王女を結婚させたいと目論んでおり、それで首斬りの法を提案した人物であった。
自分の目論見が失敗しそうなことを悟った宰相は、王に「もしこの若者がそんなに豪傑で知恵者なら、歌う鶏を持って帰りますでしょう。もし見事に持ち帰ることができましたなら、王女さあはあの若者のものとなります。しかし、もし持ち帰ることができなければ、死んでもらうことになります」と言い、末息子の命を危険にさらそうとする。
末息子はそれを承諾し、出発前、王女に三つの植木鉢を渡して「さあ、お前にこの三つの植木鉢をあげよう。一週間に一度、水をやってくれ。一つ枯れたら私の力の一部が、二つ枯れたら半分が尽きてしまったということだ。三つとも枯れたらもう私が死んでしまったということだ」と告げる。
末息子(若者)は食料を携え馬に乗り、1か月2か月、さらに3か月進み続け、在る時岐路にたどり着く。片方には『この道を行く者はもう戻れない』と書かれ、もう一方には『幸運の道』と書かれており、末息子は迷った末『帰れない道』を進む。
その道のそばに一人の老婆が現われ、「もしこの道を行きなさるんなら、どうしたらいいか教えてあげるから」と言って助言をする。「この道を行けば、帰りには、あんたの欲しいものは何でも持って帰れるんだからね。あんた、歌う鶏を持って帰らなくちゃならないんだろ。広い野原に出たら、大きな木が見えるまでお行き。そこには大きな鳥カゴがあって、その中にはあんたの欲しがっている歌う鶏がはいってる。だけど、その鳥カゴに近づいちゃいけないよ。カゴを守っている7つ頭の怪物が見えるはずだ。もしその怪物の目が開いていたら、その時には鶏を取ることができるんだよ。怪物が眠っている証拠だからね。だけども、もしその目が閉じていたら、用心おし。それは怪物が目をさましている証拠だからね。」といったものや、そのあと待ち構えるさまざまな危険とそれへに対処法を教えてくる。
何か月もかかったものの、老婆の助言の通りすべての難題をクリアした若者は、歌う鶏を手にして老婆のもとに戻ってくる。
老婆は若者をねぎらい、休んでから出発するように勧め、若者をもてなす。
その夜、鶏は若者に話しかけて、あの老婆は若者を殺して自分を奪おうと目論んでいると伝える。老婆は若者を雌犬に変身させてしまおうとしているので、老婆がしゃがみこんだ好きに銀の棒で老婆を打てば老婆をメス犬に変身させることができる、と伝える。
若者は鶏に教えられた通りにして。老婆をメス犬に変える。
そうして若者は、歌う鶏とメス犬を連れて帰路につく。
一方、王女は植木鉢に水をやるために屋上に昇った。2つの植木鉢は枯れていたが、3つ目の植木鉢からは若葉が出ていたので。夫(末息子)の無事を確信した王女は喜びのあまり踊り出す。その喜びを王と宰相に伝えているうちに、若者が帰還するのが屋上から見える。
城についた若者は、護衛と番人のもと、10日の間王女の部屋で過ごす。それから、自分の持ち帰ったものを周囲にお披露目するように王に言う。
皆が集まり、鶏を見せ、鶏は両方の翼を広げ大きな羽音を立てて、口を開いて人間の言葉をしゃべり、歌を歌った。鶏が歌い終えると、若者は金の棒でメス犬を打って老婆の姿に戻して見せ、銀の棒で打ってまたメス犬に戻して見せる。
若者はこの老婆の経緯を聴衆に説明し、さらに鶏が若者の身に起こったことを一つ残らず話し、最後に「ごらんなさい、この若者は不思議なものを一つ持って帰るために旅に出たけど、2つも持って帰りました」と口上を述べる。
納得した王は、若者のこれからの希望を聞く。若者は「私は妻を一緒に連れて行きたいと存じます。これは私のものなのですから」と言い、そうして王女を馬の背に乗せ、母親のいる家に戻る。
家に帰りついた若者は、王女を母に見せ「ほら、この娘がわかるかい?この娘のために、母さんの二人の息子、おれの二人の兄さんが死んだんだよ」と言って、剣を引き抜き、王女の首を斬り落とす。
そしてその首を、「ここに100番目の首がございます」といった手紙と共に、王のもとへ送り届ける。
おしまい。
…えええええ!!
えええええええええええええ!!!
あっ…ハイ…結ばれておしまい…とかではない…あっ、ハイ…
| 語り手の出身地 | モロッコ |
| IFA番号 | 3321 |
| AT番号 | 465Ⅱ;480;554 465Ⅱ;559A(Andrevev)Ⅰ;653A;945Ⅱ |
| 元資料 | Dov Noy;Sibim sippurim we-sippur mip-pi Yehude Maroqo , Jerusalem 1967 ヘブライ語 |
| 訳者 | 小脇光男 |
口をきかない王女に口をきかせる頓智話で、「笑わない王女を笑わせる」「王女に『それは嘘だ』と言わせる」等数多くの類似の話と共に難題話に属する物語で広く世界中に分布する。ただ最後は主人公と王女の幸福な婚姻で終わるのが普通であるが、本書では主人公の王女や国王へび復讐で終わっているのは興味深い。
pp。205‐206
…ということで、いわゆる他の国にあるような似た話でインターネット上で読めるものも見つけてきました。
このお話がとくにすごいなぁと思ったのは、「王女が若者に想いを寄せるところをしっかりと描いている」のに、こういう結末に持っていくところというか。
てっきり「ツンデレ姫と機転の利く若者のお話」という感じのお話で終わるのかと思っておりましたら…なんという裏切り。でも王女が殺してきた99人のことを考えると、それはそれで筋は通っている印象です。
(そもそもは宰相の策に踊らされていたことを考えると、王女がかわいそうだという見方もあると思いますが)
日本の昔話でも異類婚姻譚なんかを読んでいるとじとーっと嫌な気持ちになりますが、これはガタッと裏切られるカンジがあって、いやはや、なんとも。
息子は剣を引き抜き、娘の首を斬り落としてしまった。そしてその首を、娘の父、王のもとに、一通の手紙をそえて送った。手紙にはこう書いてあった。
p.37
『ここに百番目の首がございます。この首が付いていた女のために、王さまは99人もの命を奪っておしまいになりました。そこで、ちょうどきりのよい数になるように、もう一つ首をお送りいたします。私は人殺しの王さまの息子になど、決してなりたくはございません。そんな人の娘の夫にもなりたくはございません。この娘のために、私の二人の兄が命を失ったのですから』
ユダヤ民族の心意伝承、なのでしょうかね。どのみち王女自身は王や夫(末息子)といった「男性の所有物」として扱われている印象なのでかわいそう感はぬぐえませんが、まあ民話なのでフィクションとして男性に向けた啓蒙話として語られていると考えたいな、とは個人的に思います。
もしこの先、類話でかつ別の結末のお話があったら紹介したいです。
「ユダヤ民話40選」はヘブライ語やラディノ語からの直訳という特徴のある民話集
これは欧米語からの重訳ではなく、ヘブライ語やラディノ語からの直訳であるところが他の民話集とは違うところである…そうです。
そのせいか、読みづらいッ部分がひじょうに多かったので、「お話の筋だけ知りたいんやー!」という方にはおススメ…しません。
ユダヤ民族の微妙な言葉のあや」に心を寄せながら読みたい、という方は良いと思います。
▽「ユダヤの歴史」とかのほうが気になる方は
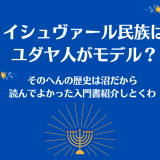 イシュヴァールはユダヤ民族が元ネタ?まぁ「わかるユダヤ学」手島勲矢著 でも読むのはどうや【鋼の錬金術師】
イシュヴァールはユダヤ民族が元ネタ?まぁ「わかるユダヤ学」手島勲矢著 でも読むのはどうや【鋼の錬金術師】
 ガブリエル×マリア性交疑惑、ギリシャ語とヘブライ語聖書で追ってもらった~植月惠一郎『ラヴクラフトの〈反転〉する恐怖』一文より
ガブリエル×マリア性交疑惑、ギリシャ語とヘブライ語聖書で追ってもらった~植月惠一郎『ラヴクラフトの〈反転〉する恐怖』一文より