谷真介著「キリシタン伝説百話」を読んでいたら、

天草四郎は実は原城で死んなくて、龍になった
という伝説があるのを知った。
気になったので調べてみた。
このコラムはその調べてみたことの軌跡として公開する。
…主よあなたは神の子キリスト
永遠のいのちの糧
あなたを置いて誰のところへ行きましょう…
目次
天草四郎の龍化伝説 × 7 ~地図も添えるね~
伝説で言及される場所の地図
青い十字架…今回の伝説言及の地
伝説 × 7
国会図書館デジタルコレクションで調べられた資料と、谷真介「キリシタン伝説百話」から引用してみる。掲載誌の出版年が古い順に並べる。
① 管内実態調査書 天草編↓
池島には雌雄二頭の大龍がすんでいたという。寛永一五年三月一七日、切支丹の籠る原城は陥落した。そのとき大将天草四郎時貞は龍玉を取り出し、天に念じて曰く「ああ神よ、吾等の九族に幸いを垂れ給え」と、沖合の幕府軍々船に向かつて龍玉をなげかければ忽ち咫尺を弁ぜぬ黒雲漲り二頭の大龍現われ、物凄い大暴風雨が起こり敵の軍船は転覆沈没し、大龍と共に海底深く沈み、同時に原城は落城した。その龍が池島に来り、二つの穴に沈んだといい、この穴を雌龍穴、雄龍穴と呼んでいる。後年旱抜の続く年はこの島に雨乞いをすることになつている。
(引用:「管内実態調査書 天草編」熊本県警察本部警務部教養課出版年月日,1959年,p.15)
②天草ガイド : 観光熊本 ↓
池島
松島町今津。メス・オス二頭の竜がすんでいたという。キリシタンの乱で、島原に原城がおちるとき、大将天草四郎は天に祈って竜玉を幕府軍の軍船にむかって投げた。すると黒雲にのって二頭の竜が現れて大あらしになり、敵舟はテンプクして、沈んだ。その龍は池島にきて二つの穴に沈んだ。
メス竜穴、オス竜穴がある。干ばつのときは、池島で雨乞いする。
③熊本の伝説 (熊本の風土とこころ ; 9) ↓
池島
天草郡松島町今津
総帥天草四郎は、今はこれまでと思ったか、十字をきって天に祈ると、幕府軍の軍船に向かって竜玉を空高く投げた。すると今まで晴れていた天はにわかにかき曇り、二頭の竜が現れて大暴風になり、幕府の軍船はたちまち転覆してしまった。
二頭の竜は体が傷つき血が流れ出して海を真赤に染めながら大矢野島の方へ泳ぎ渡っていった。池島に泳ぎついて海中にある二つの大穴に沈んでその島の主になったという。一説には竜は四郎の化身と伝えられ、原城が落ちた時四郎は竜に姿を変えてこの島に逃れたという。干魃の時は池島で雨乞いをする。(熊本の伝説 (熊本の風土とこころ ; 9)荒木精之,1975年,p.200 )
④ 熊本の伝説 (日本の伝説 ; 26)↓
総帥若干十六歳の天草四郎は、燃えさかる火炎の中で十字をきって天に祈ると、幕府軍の軍船に向かって竜玉を空高く投げた。すると天はにわかにかき曇り二頭の竜が現れて大暴風になり、幕府軍の軍船は残らず転覆してしまった。二頭の竜は、傷つき流れ出した血で海を真っ赤に染めながら、大矢野島のほうへ泳ぎ渡っていった。池島に泳ぎついて海中にある二つの大穴に沈んでその島の主になったと伝えられている。一説には、その竜は天草四郎の化身であり、竜に姿を変えてこの島にのがれて来たという。
⑤「日本の民話 21」 ↓
二十七日の夜半に原城の本丸が天をこがして焼け落ちますと、四郎のいた本丸の奥の家から若い女たちがつぎつぎにその炎の中にとびこんでいくのでした。四郎のいた家は囲りを石垣でかこんであるのでそのまま残っていたのです。
天草四郎は、そのとき今はこれまでと思ったか、竜玉をとりだして、
「ああ、神よ。我らの上に幸いを垂れ給え」
と天に祈り、沖合いに錨を下していた幕府の軍船に向かって、手に持っていた竜玉を投げました。
すると空がにっわかにかきくもってどす黒い雲が舞い降りてきたかと思うと、二頭の大龍が現れ、物すごい大暴風が起こりました。
海面から二つの水柱が黒雲までつらなり、幕府の軍船がその大竜巻によってたちまち転覆し、宙に巻きあげられたかと思うと、まっさかさまに海中に沈没してしまいました。
それと同時に、四郎のいた家にも火が燃えうつり、その炎は天を赤々と染めて暗い海原までも照らしました。
城内の一揆軍は新手の攻略軍につぎつぎに倒され、その死骸は外壕や内壕に積みかさなり、出丸、二の丸、本丸のあたりにいっぱい女子供まで傷つき倒れて、その死体の上で生き残った一揆軍と幕府軍の激しい合戦が続きました。 幕府軍が一揆軍を残らず討ち果たしたのは、二十八日の午の刻(正午)でした。
黒雲に乗って海中に入った二頭の竜は、原城の陥落を見とどけると、まっしぐらに東に向かって泳ぎました。
竜の体も傷つき、首や腹、背に大傷をうけ、鮮血が海を染めて竜の通った海中は赤く濁ったといわれています。
竜は池島に泳ぎつき、海岸の岩に頭をうちつけてしばらくはあえいでいましたが、人影が無いのを見とどけて丘にはいのぼり、島のあちこちを見まわしていました。
島には昔から二つの大穴があります。竜はそれに気がつくと、それぞれ一頭ずつ穴に入って姿が見えなくなりました。そして、その穴の主となったと伝えられています。
雄竜の入った穴を雄竜穴、雌龍の入った穴を雌龍穴と呼ぶようになりました。
天草四郎は原城で死んだことになっていますが、じつはこの竜が四郎の化身といわれ、竜に姿をかえて池島に逃れてきて、その穴の主になったということです。
それ以来、天草島は旱ばつがあれば、附近の人たちは池島に集まって雨ごいをすると、黒雲がおりてきてかならず雨が降ると伝えられています。はなし 松島町樋合島 益尾幸人(五〇)
⑥ 「天草伝説集」↓
池島伝説によれば、天草四郎は、この時龍玉を双手に持ち、天に念じて「ああ、神よ、われらの九族に幸いを垂れ給へ」と、沖合にあった幕軍の船に向かって龍玉を投げると一天にわかにかき曇って物凄い大暴風となり二頭の龍が現れて、幕軍の軍船は見るまに転覆してしまった。二頭の龍は体が傷つき血が流れ青い海を真赤に染めながら大矢野島の方へ泳ぎ渡っていった。それと同時に原城は陥落したという。その二頭の龍が池島に泳いできて海底の二つの穴に沈んだと伝えられている。この穴を雄龍穴、雌龍穴と呼んでいる。また原城で討死したことになっている天草四郎は、この龍の化神と伝えられ、この島に逃れてきたものと伝えられている。
旱魃の年は、この池島で雨乞いをする。
⑦「キリシタン伝説百話」 ↓
しかし、四郎の最期には、もう一説ある。
四郎は石の壇の上で天を仰いで祈ったのち、大切にしていた竜玉を懐から取り出すと、それを沖合に浮いている幕府軍の軍船めがけて投げつけた。
すると、にわかに空はかきくもり、どす黒い雲が舞い降りてきたかと思うと、たちまち大暴風となって雌雄二頭の大竜が現れた。大竜は海にはいって海水をかくはんし、二つの巨大な水柱となって幕府の軍船を虚空にまきあげ、海面にたたきつけた。それと同時に、四郎の居所にも火がついて焼け落ちた。
海中にいた二頭の竜は原城が陥ちたことを見届けると、まっすぐ東にむかって泳ぎだしたが、からだには大傷を受け、鮮血で海を染めながら池島へ泳ぎついた。そして島の中腹にある二つの大きなほら穴のなかへ一頭ずつはいって、姿を消したという。
その後、雄竜のはいった穴を雄竜穴、雌の竜がはいったほら穴を雌龍穴と呼ぶようになったが、この二頭の竜は島原の乱で死んだ四郎の化身で、四郎は最期に竜に姿をかえて池島に逃れ、その穴の主になった。四郎のからだが雄雌二頭の竜になったのは、四郎は人間ではなく、天人であったからだという。
それ以来、天草に旱ばつがあると、付近の島の農夫たちは舟で池島に集って、竜神になった四郎に雨乞いをする。するとたちまち、じぶんたちの島の上に黒雲が降りてきてかならず雨が降る、天草四郎は死んでからも天草の貧しいものたちを救ってくれたという話である。(引用:谷真介「キリシタン伝説百話」pp.98-99,新潮選書,1987年)
上天草ガイドによって「出前紙芝居」で語られているようだ

↑「出前紙芝居あります」に『①池島の龍伝説(天草・島原の戦い)』タイトルがある。
さらに、上天草観光ガイドの会、大澤会長を中心に企画・制作した紙芝居は、子供たちに天草五橋の歴史を伝える上での、貴重な資料として今でも使われています。
雑感
前提:神話・伝説・昔話の区別
| 神話 | 伝説 | 昔話 | |
|---|---|---|---|
| 例 | 旧約聖書(創世記の天地創造,ノアの洪水伝承) | アーサー王伝説,ジークフリート伝説,弘法大師の植えた木や休んだ場所 | 桃太郎,赤ずきんなど |
| 信仰・ 伝承意識 | 事実・疑えない事実 | 事実・信ずべきコト | 虚構・あったかなかったか不確かな虚構 |
| 主題 | 国土・人類・文化の起源 | 聖なるコト・モノの由来 | 異常な幸福 |
| 時代・ 時制 | 遠い過去・神の世 | 近い過去・古へ世・中つ世 | いつでも・遠い昔 |
| 場所・ 固有性 | 異界・または今より古い世界・固有性アリ | 今日の世界・固有性アリ | どこでも・固有性ナシ |
| 態度 | 神聖 | 神聖または世俗 | 世俗 |
| 主要人物 | 非・人間 | 人間 | 人間、または非・人間 |
雑感その①雑味の少ない資料しか見つけられなかった

伝説の書かれ方が統一されすぎているような気もする…
並べてみて思ったのは、伝説の書かれ方がが統一されすぎているようにも思う…ということだ。
なのでこれは、どこかのタイミングで文章化されたものをきっかけに、一部の人が語るようになったであるとか、上記に挙げたような伝説集・民話集に収録されていったものではないか…という仮説を思い浮かべてもいるが、なにせ当方は説話研究者ではないのでそのへんの読み解き方はサッパリわからない。
「池島 龍」「天草 龍」「松島 龍」「池島 雨乞い」「天草 雨乞い」「松島 雨乞い」などでも調べてみたが(国会図書館デジタルコレクション)、まぁ…ないのである。つまり「池島の龍伝説」については、『龍の足湯の天井』のものしか情報を見つけられておらず、「池島の雨乞い」については『龍の足湯の天井』か『向陽寺の梵鐘(熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト掲載)』しか情報を見つけられていない状態である…。
雑感その②「ヌシになった」でいいのか

四郎だった龍は「池島のヌシになった」って書いてる文章けっこうあったな
「ヌシ」というのは、実は、まとまった論というのがありそうでなかった分野らしい。『学会におけるエアポケットのような領域だったのでまとめてみることにした』と伊藤龍平が「ヌシ 神か妖怪か」(2021年,笠間書院)の序文(p.7)にて述べている。
せっかく2025年に「ヌシ」というキーワードが出てくるトピックを扱うだから、ここで取り扱われている「ヌシ」の条件に照らし合わせて考えてみても面白いかとは思った。
もちろんこれは伝説であって、集めてきた文章のうち半分くらいが「ヌシ」だと表現しているので『ヌシだと言ったらヌシだ』で全く良いのであるが。
というか、ほかに四郎だった龍・池島の龍に関する詳細な伝説ないからこそ、ヌシの条件から逆算して四郎だった龍のことを想像する素材になるかもしれない。
【ヌシの条件】
1.ひとつ所に長く棲んでいること。
2.棲みかである場所が、淀んでいること。
3.その場所から、離れようとしないこと。
4.身体的な特徴があること。(蛇なら「大蛇」であること,亀なら「大亀」であること,片目がないことなど…)
5.尋常ならざる力を持っていること。
(参考:伊藤龍平「ヌシ 神か妖怪か」pp.21-22)
…だそうだ。
そしてもうひとつ興味深いのは、天草四郎がヌシになった経緯も、王道からはやや外れているということだ。
各地の例を見るかぎり、ヌシになる方法は大きく分けてふたつある。
ひとつは、ヌシの棲む池や沼の水を飲む、あるいは、禁じられたものを食べるということである。もっとも、これはタブーを破って祟りを受けているのであって、命の保証はない。(中略)
もうひとつは、受け身な方法だが、ヌシに魅入られることである。ヌシの棲む池や沼に行ってわが身を晒せば、ヌシに気に入られて連れていかれるかもしれない。ただし、容姿に自信のある方にかぎる。ヌシは例外なく、面食いなのだ。(伊藤龍平「ヌシ 神か妖怪か」p.176)
ただこれに関しては「神仏への祈願の末、龍になった」くらいまで抽象化するなら、秋田県の辰子姫伝説がある。
田沢湖(秋田県仙北市)の辰子姫伝説——むかし、辰子という娘が、永遠の美貌を観音に願ってお百度参りしたろころ、ひたすらのどが渇いて泉の水を飲み、ヌシ(龍)になったという。永遠の美貌を得る=ヌシ化するという意識が、辰子にあったかどうかは定かではないが。
辰子姫の像は田沢湖畔にあり、観光資源となっている。建てられたのは1968年、高度経済成長期下、国内旅行が盛んになり、地域の伝承が見直されつつある時期だった(国鉄のディスカバージャパン・キャンペーンの開始が1970年)。伝説が観光と結びつくことは珍しくないが、辰子がヌシ化する以前の人間の姿で彫像されている点は押さえておきたい。
(伊藤龍平「ヌシ 神か妖怪か」p.176)
先の「ヌシは神か妖怪か」という問題に立ち返ると、わたしは、ヌシとは「神でもあり、妖怪でもある」存在だと考えている。小松和彦は、祀られた超越的存在を神とし、祀られていない超越的存在を妖怪としている(※14)それでは、「祀られている/祀られていない」とはどういう状態なのだろうか。
一般的に「祀る」てゃ、社や祠を設け、定期的に儀礼をおこなうことをいう。これを基準とすれば、全国のヌシには、祀られたものと、祀られず、ただ恐れられているだけのものがあり、前者は「神としてのヌシ」、後者は「妖怪としてのヌシ」と、一応は定義づけられる。それをふまえたうえで、祀られるきっかけになった感情に注目しなければならないだろう。
ここで、ヌシが、人々に恐怖心を抱かれていただけではなく、畏怖の念を抱かれていたことにこそ注目すべきだと思う。畏怖の念は、神への信仰心にも、妖怪への恐怖心にも、どちらにでも振れるものだ。だから、より正確に言うなら、ヌシには「神として祀られているヌシ」と「現在は祀られていないが、神に転ずる可能性があるヌシ」がいることになる。
(伊藤「ヌシ 神か妖怪か」p.41)
現状の調べでは、池島での雨乞いはもう行われてなさそうなので、四郎だった龍は『祀られていたが、祀られなくなったヌシ』になるのかもしれない。『雨乞いを行ってないだけで祠や社などはある』可能性もあるが。
雑感その③干ばつのさいの雨乞い祈願の対象なのか
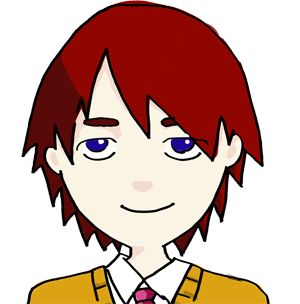
天草四郎はキリシタンだったワケだけど、キリスト教って一応、唯一神教なんだよね…
つまり、キリスト教は実態はどうあれ「神はひとり」という世界観を標榜している宗教であって、四郎はキリスト教徒だったわけだが、
そんな四郎が化身した龍に祈って雨乞いをするというのは、ギリ聖人枠(※1)で『雨の取次として崇敬してます』くらいには言っても、明確に『祈願対象』として扱うのはちょっと浮かばれねぇ(※2)んじゃないのか…?
(※1)天草四郎は列聖はされていない。(→別ウェブサイトでコラムあり)
(※2)仏教の世界観から生まれた用語だけど、日本語として浸透している言い回しなのでわざと使用。
という全く余計なお世話なことを思った。
で、よく読んでみると、四郎だった龍が明確に「人々の祈りを受けて、人々に恵みの雨をもたらしている」と読めそうな語りを入れているのは谷真介版のものだけであるのも気づいた。
これに関しては、当方この伝説の語り手たちの背景すらもまっっっったく知らないド素人なので、もうすこし時間をかけて調べて…何か書けそうだったら書くし、この考え方が本当にまったく余計なお世話だと判明したら、天国で天草四郎およびこの伝説を語り継いだ方々に土下座する準備をしておく………。
一応言っておくと、当コラムライターは「キリスト教は実態として拝一神教だ」と解釈したいという欲望と属性を持っている。
天草四郎が龍になって、池島のヌシになって、何かしらの形で敬われている…ということ自体は、私の願望に合致してしまうかもしれない。だからこの周辺に執着してアレコレ調べてしまっているのだと思う。
ただ、この考え方は現代日本人のキリスト教徒たちからはほぼ同意を得られないと認識している。かつてこの国に伝わったキリスト教の世界観に己の人生を解釈させたキリシタンたちはどうだったのだろうか。
私が、いまより深くそれを知ることができることを祈って、このコラムを閉じる。
———髑髏の丘で磔刑に処された男の声が聴きたくて、こんなところまで来てしまった―――
参考文献
国会図書館デジタルコレクションのリンクは引用ごとに張ってあるので割愛。



