こちらの動画を制作するにあたり、監修役のひとりから
・そう思うに至った経緯
・参考文献
・可能ならば箇所の引用をすること
と指示があったので、このページにまとめます。
基本的には私は宗教学にも神話学にも説話研究の分野もすべてにおいて素人です。なので、私の述べることも戯言です。しかし、シロウトの私ですら認識している知識があり、それは
「三輪山神婚説話をもってして、日本人は蛇を忌避していなかったと言える」
「(現代人が)日本(だと漠然と考えているであろう領域)において、ここに住む人間たちはいつの時代もどの地域も蛇を神聖な存在として考えていた」
という意見に反しますので、とりあえず記します。
このコラムは「三輪山神婚説話」で検索したらけっこう上位に表示されるようになってしまいました。想定外です。(Youtube動画制作→チーム内で補足を求められる→ウェブ記事を制作というユーザー動線しか想定していませんでした)。しかしながら「三輪山神婚説話」というキーワードで検索できる属性の方におかれましては、まったく不要の知識を述べているウェブコンテンツであることをお伝えしておきます。このコンテンツは、そんな用語にすらたどり着かない方々を想定したコンテンツです。ここで述べていることは、「よくわからなすぎてかえって研究ではとりあげられないゾーン」にむけた話をしていると認識していただければ幸いです。
目次
前置き
「そんなこと言うヤツおらんやろ」
「日本には三輪山神婚説話がある、(ゆえに)日本人は蛇を邪悪なものと考えない」なんて言うヤツはいない。ストローマン論法だ!
「(現代人が)日本(だと漠然と考えているであろう領域)において、ここに住む人間たちはいつの時代もどの地域も〈蛇〉を神聖な存在として考えていた」なんて言うヤツはいない。ストローマン論法だ!
…と思われる方もいるかもしれません。すみません、そう思われるのならソレで大丈夫なので、こんなどこの土の塵が書いたともしれない粗末な書き物を読むことに可処分時間を使わずに、もっと大事なことに時間を使っていただければと思います…。
補足的に申し上げておきますと、「実話怪談/怪談実話」と呼ばれる営みを愉しまれている方の中に、たとえば『〇〇さんという方から聞かせていただいたお話なんですが、この方、若い時に蛇をあやめてしまって、以降〇〇な現象がおきて…〇〇で…』といったお話に対して「日本人は蛇を神の使いだと考えていた」という意見がことごとく寄せられているのを確認しています。(とはいえ一応断っておきますと、この「ことごとく」は主観です)なので、そういう属性に少しでもリーチできたら、の想いで、「よくわからなすぎてかえって研究ではとりあげられないゾーン」の話をしていると認識していただければ幸いです。
聖書は蛇を邪悪な存在ととらえるか?
知らねー!
少なくとも私(平成生まれ/四国生まれ育ち/真言宗僧職を親に持つ/日本語話者/日本国籍/プロテスタントキリスト教徒)は思ってないけどねー!?
とりいそぎノースロップ・フライを守備表示で召喚するぜ!!
「創世記」二:九で二本の木が言及されている。生命の木と善悪の知識の禁断の木である。隠喩的には、それらの木は同じ木である。禁断の木が明らかに、われわれが今日知っているかたちの性的体験の発見といくらか関係があるように、生命の木は、「失われた男根(3)」――今日のわれわれには失われた方法で生命を付与する者――と呼ばれている神話のひとつである。禁断の木には這いながらのろのろと、そしてぐにゃぐにゃと木から離れていく呪われた蛇がいるように、生命の木には、もし同じイメージが適用されるならば、クンダリーニ・ヨーガとして知られているインドの象徴体系のように、枝を登っていく知恵と知識の直立した蛇がいることだろう。「創世記」に後者は出てこないが、いかなるイメージも内在的に善であるとか悪であるとか、あるいは黙示録的であるとか悪魔的であるとか、きまっているわけではない。それが何であるかは文脈次第なのである。エデンの物語におけるその役柄から、蛇は通常、聖書の伝統では不吉なイメージである。しかし蛇は真の知恵の象徴(「マタイによる福音書」10:16)や治療の象徴(「民数記」21:9)にもなりえたのであった。ギリシャ神話の場合とまったく同様であった。実のところ、蛇崇拝に対するヒゼキヤ王の恐れは「創世記」の蛇に帰せられる「狡猾」な策謀の反映かもしれない。
(ノースロップ・フライ「大いなる体系」pp.211-212)
▽動画にもしてみたけど大したことは言ってない
説話の表象が、その「民族(?)」の意識を表現しているという考えそのものの妥当性や、如何に
この考え方自体、一種の説話研究の研究手法なのだと認識しています。たとえば、現代人における蛇の表象の研究をしたかったら、民間伝承を集めて分析するアプローチではなくて、大量のアンケートをとるであるとか、世代と地域を区分しつつ文学やアートや漫画やアニメを分析するとかのほうが調査の方法としては適切なのではないでしょうか?
逆に言うと、「日本には三輪山神婚説話があるから~」といったコトを言ってしまう方というのは、現代日本における蛇の表象が必ずしも邪悪とは呼べないいことから、逆説的に『〈古来〉より〈日本人〉は蛇を邪悪な存在とは考えていなかった』と思ってしまい、それで、日本神話では有名な三輪山神婚説話と結びつけて考えてしまったのかもしれません。
言いたいことには妥当性があるが、引き合いに出した例が妥当ではないがゆえに、先の意見の信ぴょう性が疑われてしまう…
となると、もったいないような気がします。
なので、こんな土の塵の書いたコラムはさておいて、ここで言及している書籍などでまだ読まれたことのないものなどがございましたら、お手に取っていただくといいんじゃないか…とか思いました。
三輪山の神は蛇の本当に蛇の神なのか!?
(「そんなこと言う奴おらんやろ…」と思うかもしれませんが、一応………)
三輪山の神が蛇の神であるという伝えは、『日本書紀』雄略天皇七年の七月の条に見える(坂本・上-472)。
天皇が側近の少子部蜾蠃(ちいさこべのすがる)に、三諸丘の丘の神の姿を見たいから捕らえて来いと命じる。蜾蠃は諸岳に登り、大蛇を捕えて来て天皇に示す。大蛇は雷鳴のようにとどろき、目を輝かせる。天皇はおそれて、大蛇を見ずに御殿の中にはいり、神を丘に放させる。蜾蠃には、あらためて「雷」と言う名をたまわる。
蛇の姿ではあるが、その性格は雷神である。三諸岳とは三輪山のことである。ミモロとは、神霊の依りつく神座をいう。三諸岳はつまりは神なび山ということになる。
(小島瓔礼「蛇の宇宙誌」1991年,pp.24-23)
あとこれは完全に個人的な興味なのですが、個人的には、三輪山神婚説話に似た構造の神話・伝説を持ちつつ現代においては多くがキリスト教徒に改宗している中国少数民族(ミャオ族とかイ族とか)、台湾原住民族(ルカイ族とかパイワン族とか)あたりの方々が現代において『蛇』なるものをどう考えているのか(どうも考えてないのか、も含めて)…などを知りてぇもんだな…とか思っています。先行研究があったらご教示ください。(コメント欄解放してます)
いくつかの論点整理~
・「神話」は宗教の構成要素の一部である(祭祀とか奇跡とかそういうのがある)
・「日本」とは何か?時代の特定をせずにこの定義が使えるとは思わない。
・「蛇」の生物としての種類の地域差を考えているか?
・「三輪山神婚説話」は、〈日本〉における「蛇の聖性」を保証する説話か?
・『日本』の伝説における蛇の表象で、退治される〈鬼〉が「蛇」である伝説も大量にあるが。
・『日本』の民話のおける蛇の表象で、…たとえば『異類婚姻譚』における「蛇」の扱いは、『婚姻は恥ずかしい/みじめ』であると表現され、蛇婿においては明確な殺意を持って殺害される。
・…が、これを「蛇」に対する日本人の意識と考えてよいのか問題はまた別だと思われる。
全部細かく見てると手に余るので、「日本における説話研究者による、日本の説話における〈蛇〉のとらえ方」のみ紹介してみます。(このコラムを書いている人間が、ここ数年民間説話を読むのが趣味だからです)
もちろん、当方はド素人です。私がここで紹介する資料以外にも色んな資料が存在するはずです。
ド素人でも触れられる距離に、冒頭の信念がおそらく覆される知識がありましたので、言ってみる…というカンジです。
ただ、「ちょっと調べたらそうは言えんことは一目瞭然」という意見ほど、けっこう忘れさられて、基礎的な研究があるのにそういう論を置き去りにしてよくわからん語りが主流になる…みたいなのは結構あるようなので、改めて書く意味みたいなのもあるのかな…と思いました。
研究者と、そうではない人たちの間の距離が縮まったらいいな…という祈りのもと紡がれたコラムだと思っていただければ幸いです。
注意書き
・「柳田國男がこう書いてるから日本はコレだった」「折口信夫がこう書いてるからそれが正しい」という論は退けます。(そういうのは柳田論、折口論としてやっていただくのが妥当だと思います。)
・同じような理由で吉野裕子氏のやつも振りかざしたりしないでいただきたいです。以下に紹介する論者たちはこれらの論を踏まえて論じていると認識しています。
・「三輪山神婚説話」そのものは論じません。それを論じるまでもないトピックだからです…。
そのうえで、説話研究者たちの述べる「日本の説話における蛇の表象」をいくつか紹介
以下、
現代で『日本』だと思われている範囲の、説話における蛇の表象が、ただ〈神聖な存在〉ではない
…ということを示す引用が並びます。
日本における蛇の表象について~神話・伝説・昔話の研究者たちの意見やいかに~
蛇は世界中の多くの民族のあいだで崇拝されたり、またシンボルとして、もてはやされてきました。神話や説話、彫像、絵図などに、古くから登場しています。
(引用:「ガイドブック日本の民話」日本民話の会/編p.247)
わが国では、蛇が男に姿を変えて、人間の女性とちぎりを結ぶという三輪山神婚説話が、古い文献に記されています。『古事記』にのる話では、女性は懐妊しますが、男の正体がわかりません。そこで男の着物の裾に糸をつけて跡をたどっていくと、三輪山の神の社に到着しました。男は蛇身の大物主神(おおものぬしのかみ)であったのです。「蛇婿入り」の苧環型の話と構成はおなじです。蛇と女性とのあいだにできた子が一族の祖となるという、九州の緒方氏や越後の五十嵐氏の伝説には、蛇を神霊と見なす考えかたが背景にあるようです。蛇は脱皮や水陸両棲の習性を持つことから、蛇を神格化する観念が生まれたと説かれます。
しかし、時代が下ると蛇に対する信仰が失われ、蛇を忌避すべき邪悪なものとする考えかたがあらわれてきます。嫉妬のあまり蛇体に身を落とし、鐘の中の男を焼き殺してしまう「安珍清姫(あんちんきよひめ)」の話は、それを代表しています。
「蛇婿入り」の水乞い型で、枯れた田に水を与える水神としての役割を持つ蛇が、最後に殺されてしまうのも同様です。蛇の正体が発覚したために子を残して去る「蛇女房」も、あわれな結末をむかえてしまいます。
伝説として伝わる「蛇ケ淵」「蛇沼」には、おそるべき大蛇がひそんでいるとされます。これは、水神信仰が零落した形と言えます。蛇身となった「八郎太郎」を十和田湖から追い払うという伝説も、神から邪悪なものへと信仰をうしなった蛇が退治される姿と言えます。(花部)
↑ここで花部英雄は
「神話の蛇」→「伝説や民話の蛇」という時代的な零落があったとみているようですが、どうも最近の研究ではそういうことでもないらしいです。(次に紹介する小松和彦とかの論がソレなんかな…?)
ただ、伝説や民話の蛇において、

説話研究者たちは「現代で『日本』だと思われている範囲の、説話における蛇の表象が、ただ〈神聖な存在〉ではなかった」と考えている…
ということを示すためにこれを引用しました。
次に、小松和彦を引用してみます。小松は、上記の意見を退けて、蛇神信仰と説話における蛇の表象の違いは時代による零落ではない説を推しているようです。(たぶん…)
(水乞い型の蛇聟譚を指して)このタイプの昔話群のうちで、「蛇」が聟になる話のほとんどが、嫁入りして行く途中で人間の娘が知恵を働かせて蛇聟を殺してしまっている。したがって、こうした昔話を読む限りでは、水を支配するものとしての蛇(神)という観念が民俗社会にあるにもかかわらず、蛇と人間の女の婚姻に対しては、人々は否定的な考えを持っていたことになる。
(1998年小松和彦「異界を覗く」p.84洋泉社)
「異類聟・嫁入り」型の昔話をみる限りでは、「鬼」や「猿」の場合は、どちらかといえば、否定され排除される異類とみなされ、「蛇」の場合には、肯定と否定の間をさまざまな形で揺れ動いているのがわかる。したがって、人びとは「蛇」に対してとくに両義的イメージを抱いていたらしい、ということになるであろう。つまり、「異類聟・嫁入り」型の差異の多様さは「蛇」に対する人びとの両義的態度の揺れの大きさを如実に反映しているわけである。
(1998年小松和彦「異界を覗く」p.92洋泉社)
しかしながら、どのみち「現代で『日本』だと思われている範囲の、説話における蛇の表象が、ただ〈神聖な存在〉ではなかった」ということを提示するには十分な資料だと思いますので、ここに記します。
たとえば「ヌシ」の扱いやいかに
次に、伊藤龍平氏は、説話などで語られている「ヌシ」という存在の7~8割が「蛇」ではないかということにふれつつ…
ヌシの種類ということでいえば、きわだって多いのが蛇と龍である。信用できるデータがないので正確なところはわからないが、わたしの調べた感触では、全体の七~八割を占めると思われる。とくに蛇のヌシは多い。身体的特徴としては、並外れた巨体の大蛇がもっとも多いが、ほかにも、角や耳があったり、白や金の体色をしていたり、極端に小さかったり、身体の一部が欠損していたりする場合もある。蛇は、山のヌシや、家屋や蔵のヌシであることも多い。一方、龍が山や家屋・蔵のヌシになった例はなく、相違がみられる。
伊藤龍平「ヌシ:神か妖怪か」p.71.
そのの対処法として以下の6パターン分類を提案されています。
(1)退治する
(2)どこかへ追放する
(3)生きたまま封じ込める
(4)神として祀りあげる
(5)契約を交わす
(6)ヌシをヌシのまま利用する
(伊藤龍平「ヌシ:神か妖怪か」p.53-55)
ちなみに、日本全国津々浦々に残る「ヌシ」の源流として『夜刀神』の伝承を提示されています。夜刀神伝承を知らずに日本の蛇の表象について語るヤツは私以上のシロウトだと見なします(この伝承は説話研究書だけでなく、神道入門書などで必ずといっていいほど言及される存在なので)
私以上のシロウトは、こんなコラム読んでないで、ここで紹介している書籍でも読んでください。
クリティカルな論ではありませんが、いずれにせよこれも

「現代で『日本』だと思われている範囲の、説話における蛇の表象が、ただ〈神聖な存在〉ではなかった」ということを示す例
なので示してみました。
世界の三輪山神婚譚類話の比較
このへんは、動画ではテンポの問題で追加した一文で、実はハッタリ部門です。世界の三輪山神婚説話の類話は、管見では
中国
中国少数民族
台湾原住民族
あたりに似た説話があると聞いていまが、いずれも、その民族の首領格の家系の始祖神話的な役割を担っている…ということで、日本と似ているカンジがあります。これだけで言うと世界の三輪山神婚説話はやっぱりそれなりに神聖な存在として蛇が扱われたんだ~という論の補強になりそうな感じもします。(「死の神話学」収録 斧原孝守氏による『雲南少数民族の死の起源神話』 ,「雲南の民俗文化」編:飯倉照平,張麗花・高明 編訳「木霊の精になったアシマ 中国雲南省少数民族民話選」)
しかしながら、少なくとも台湾のヤツは日本と似たカンジで「蛇と結婚するのは恥ずかしい」という忌避感がありつつ、頭目筋の始祖神話になっていきます(「台湾原住民族文学選⑤神々の物語 神話・伝説・昔話集」紙村徹 編)。
ふしぎな印象ですが、
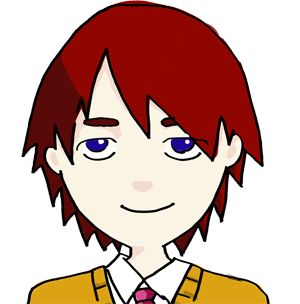
現代人の価値観を単純に当てはめただけでははかりかねる部分があるのだろう
と思わせてくれる説話です。
そして、これもまた素人的な管見ですが、「苧環(針糸)モチーフ」という点でのみ見ると、ヨーロッパにも似た話があることも認識しています。
→スイス採集、小人が人間と接点を持たなくなった由来の伝承(スイス版ルンペルシュツルツヒェン)
→フランス(ブルターニュ)、天使と人間の婚姻譚、鍵穴除きのモチーフ?
→パンツィ・マンツィ
→ルーマニア「聖母子像」の由来伝説、かつ『死』との異類婚姻譚要素のある昔話
このあたりはおいおい、自分なりに深めていけたらいいなぁと思っています。
…ということで、

現代で『日本』だと思われている範囲の、説話における蛇の表象が、ただ〈神聖な存在〉ではない

なので、三輪山神婚説話を以てして「日本人は蛇を神聖な存在として考えていた」という論は展開できない…
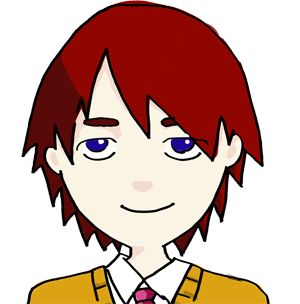
日本人の蛇に対する表象は、地域差や時代による違いがある。蛇を邪悪な存在の化身として語る日本人も確かにいる
という話でした。
翻って言うと、日本人プロテスタントキリスト教徒が蛇を邪悪な存在の化身だと考えて表現していたとしても、それは妙なことではないということにもなるかと思います。私は動画の冒頭で言及したような意見については『私にとってそうではない』と言っているにすぎません。
参考文献リスト
おまけ~民間伝承系と親和性の高い雑語り集め~
 異類婚姻譚雑語りとキリスト教disは近接しているが、一神教に帰依してない人たちが怒ってくれているので慰められてる
異類婚姻譚雑語りとキリスト教disは近接しているが、一神教に帰依してない人たちが怒ってくれているので慰められてる

