↓ こちらのコラムを作った動機が覆されてしまった(かもしれない)話を書く。
原題「Study in Scarlet」は旧約聖書雅歌4:3「あなたの口は紅い糸のよう」から。
(引用:緋色の研究 ピクシブ百科事典 2022/6/3 22:00時点)
…と「ピクシブ百科事典」に『緋色は雅歌由来』ととれる記述があったことから、
雅歌ー緋色・アダルトポエムー赤井秀一/諸伏景光(名探偵コナンの登場キャラクター)
を関連付けるコラムを書いたのだが、どうもこの「緋色」が『雅歌』由来というのはどうもあんまり有力ではないっぽい。曲がりなりにではあるが、書籍や論文を調べてみたのでその軌跡を書くこととする。その名のごとく
「緋色の研究」研究―「『緋色』の研究」
“Research of scarlet” …or…” Study of scarlet”
(「習作」「エチュード」の意味はなくなってしまうが)
…とでも言うべき営為になってしまった。
アーサー・コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」シリーズ第1作目となる「緋色の研究(緋色の習作/緋のエチュード)」。このタイトルに関連する、作中のホームズの台詞は次のようなものである。
「指輪だ、君、指輪なのだ。そのために舞い戻った。万策尽きたとしても、この指輪でいつでも罠を仕掛けられる。やつはいずれ、僕の手に落ちるよ、博士――二対一で賭けてもいい、落ちる。今回は君に感謝せねば。君なしでは出向かなかった。そして、生涯最高の題材に出会い損なっていただろう――緋のエチュード。
ふふ、ちょっとした絵画の名付け方を借りてもいいではないか。殺人という緋色の糸が、現世という無色の綛糸(かせいと)に混紡されている。我々の使命は綛糸を解き、緋の糸をより分け、残らず白日の下に晒すことだ。さて、まずは昼食、そのあとノーマン=ネルダー。彼女のアタック、ボウイングともに輝かんばかりだ。何だったか、絶妙に演奏するショパンの小品は。トゥラ・ラ・ラ・リラ・リラ・レ。」
(大久保ゆう訳「緋のエチュード」 第4章ジョン・ランスの言い忘れ )
このこのコラムでは、この「Scarlet」の由来について2022年のインターネット情報に混乱が見られたので、調べた軌跡を記していく。英語文献には当たらないのでご了承いただきたいが、それは筆者が英語超絶激ヨワの民であるのと、日本のシャーロキアンの方々に畏敬の念を抱いているからでもある。
アーサー・コナン・ドイル自身が「緋色の研究/緋色の習作/緋のエチュード/A Study in Scarlet」の『緋色 /Scarlet』の由来に言及した記録があるワケではないっぽく、ファンたちの考察が諸説ある状態。
目次
「緋色/Scarlet」はどこから?―ギリシャ神話説×1 聖書説×2 西欧の普遍的な文化説 etc…
オウディウス『転身譜』第六巻「ピロメーラーの悲劇」説-笹野史隆氏

ギリシャ神話の系譜に、「緋色の糸を、告発と復讐のきっかけに使った」というお話しがあるみたい。
『シャーロック・ホームズ大事典』の「《緋色の習作》(題名の由来)」の項(筆:笹野史隆)で、この題名は古代ローマの詩人オウディウスの『転身譜』の第六巻にある「ピロメーラーの悲劇」に由来しているとして、ローゼンバーグの説が否定されている。
(水野雅士著「シャーロック・ホームズと99人の賢者」pp.21-22
(中略)
《緋色の習作》自体が復讐の物語であることを考えると、この題名に秘められた意味の起源としては、どうやら笹野説に分があるといえそうだ。
アテーナイ王パンディーオーンとゼウクシァベーの娘。プロクネーの姉妹。パンティーオーンは国境の問題でテーパイのラブダコスと争った時、トラーキア王テーレウスの来援によって勝利を得たので、プロクネーを彼に与えた。二人のあいだにイテュスが生まれたが、テーレウスはピロメーラーに恋し、プロクネーが死んだと偽わって、彼女を迎え、犯したのち、彼女が告げることができないように、その舌を切り取った。しかし彼女は長衣(ペプロス)に織りこんで、プロクネーに自分の不幸を告げた。プロクネーはピロメーラーを探し出し、イテュスを殺して、煮て、テーレウスに供した。姉妹は遁れたが、テーレウスはこれを知って、斧をつかんであとを追い、二人はポーキスのダウリス Daulisで捕えられんとした時、神々に祈り、ブロクネーはナイチンゲールに、ピロメーラーはツバメに、テーレウスはヤツガシラ(戴勝)となった。ローマの詩人は姉妹の役を反対にし、テーレウスの妻はピロメーラーで、ナイチンゲールにはピロメーラー、ツバメにはプロクネーがなったとしている。
(『ギリシア・ローマ神話辞典』)
この織り込んだものが「白いとの地に緋色の糸で文字を織り込ん」だということらしい。
水野雅士氏はこの説推しのようである。
↓ こちらの pp.21-22 にて言及。

シャーロック・ホームズと99人の賢者
↓ 水野氏の書籍の資料として挙げられていたのが、 「《緋色の習作》(題名の由来)」 項目

シャーロツク・ホームズ大事典
聖書ヨシュア記説-小林司/東山あかね夫妻が紹介したサミュエル・ローゼンバーグ氏の見解
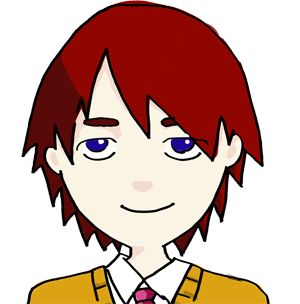
聖書には、緋色の糸を使って難を逃れた遊女のお話があるんだ
ローゼンバーグによれば、「緋色の糸」は『旧約聖書』の「ヨシュア記」第二章に由来していて、二人のスパイと遊女ラハブの話に出てくる「緋色のひも」をさしているという。
(水野雅士著「シャーロック・ホームズと99人の賢者」p.20)
ものすごく要約すると
エリコという城壁に囲まれた町に、ヨシュア率いるイスラエル民族が攻め入ろうとするのだが、それに先立ってスパイを2名送り込む。スパイたちはそこでラハブという女性にかくまわれる。ラハブにとってヨシュアたち(イスラエル民族)は敵のはずだが、ラハブは『イスラエルの神に畏敬を覚えるがゆえにヨシュアたちに味方する(要約)』的なことを言う。スパイたちは、いざヨシュアたちがエリコに攻め込んできた際に、ラハブとその家族たちを間違って殺してしまわないように、その目印として「緋色(赤い)紐を窓に結んでおくように」と告げる。
そういうお話である。
聖書雅歌説-出典不明

旧約聖書にある詩の中に『紅の糸』という形容は確かに使われています。が…
9) 殺人という一本の緋色の糸 六〇 (二五二 188)
(引用:第9章 引用の出典 1.聖書からの引用《緋色の習作》(「河出書房新社版ホームズ全集」第1巻)2022年6月12 日本時間19時36時点)
「あなたのくちびるは紅の糸。あなたの口は愛らしい」(旧約聖書「雅歌」第4章3節)に由来するとされています。
原題「Study in Scarlet」は旧約聖書雅歌4:3「あなたの口は紅い糸のよう」から。
(引用:緋色の研究 ピクシブ百科事典 2022/6/3 22:00時点)
聖書からタイトルを取るというのはその発想はあったぽいが、「STUDY IN なんとか」という形式はそれまでなかったらしい。なお邦訳に当たりこの「STUDY」は「研究より習作では」説があり、河出書房版とかではそう(『緋色の習作』)なっている。また元来の訳は、誤訳でもないし親しまれているという点から21世紀になった後発行のやつで「緋色の研究」のままというのもある(新潮社版、光文社版など)
これらの出典は確認できなかった。このコーナーも水野雅士氏の編集のようなので、氏の現時点での見解を聞いてみたい気もする。機会があれば…。
『雅歌』については当ウェブサイトで何度か言及したので、概要などを知りたい方はそちらを参照していただきたい。
以下、筆者による『雅歌』と「緋色の研究(緋色の習作/緋のエチュード)」の関連の考察である。これはコラムを書いてしまった手前、どうしても関連付けたいという欲求が反映されたものであることをご了承願いたい。
『雅歌』の解釈のひとつには「複数の男女による恋愛の情景が描かれている」というものがある。
(まあ、その前にどう解釈してたとしても描かれているのは「恋愛の情景」というシロモノではある。)
そこで,この作品の劇の構想をどう見るかといえば,深く村の若者を愛していた美しい羊飼の乙女が,若者のあ とを追って,エルサレムの城門のあたりに来 たとき,偶 然,結 婚式をあげてエルサレムへ と帰 還するソロモン王の美々しい行列に見とれる。輿に乗っていたソロモンはうら若い乙女の魅力に心を奪われ,そこで歌をもって問いかける。ここで 王と乙女の歌の応酬があり,さらにエルサレムの宮廷の女性と乙女の歌問答が行われ る。 しかしシュネムの乙女は若者への熱烈な思慕の情を披歴し,ソロモンのい’ざないを拒絶する。やがて乙女 は愛する若者を見出し,手を携え,互いに真情をこめて歌を歌いながら荒野のシュネムの村へと帰ってゆく。こ ういった構想ではないかと推定することは,あながち,不自然とはいえない。
(引用:植田重雄 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/5/3-4/5_3-4_1/_pdf/-char/ja)
そして「緋色の研究(緋色の習作/緋のエチュード)」は、複数の男女の恋愛や結婚が事件の動機となっている物語である。
「物語全体の主張」として、アーサー・コナン・ドイルには「これは恋愛が絡んだ物語なんですよ」という意図か、あるいは作家的霊感があったとは考えられないだろうか。
ホームズの台詞として印象的な「…太陽の下、新しいものは何ひとつない…」という言葉や、「実際なにをしたかが問題ではないのさ」という言葉の奥にあると考えられる世界観(※)は、『雅歌』と同じくソロモンが書いたとされている『伝道の書(コヘレトの言葉)』からの引用である。
7) 太陽の下、新しいものは何ひとつなく
(引用:「シャーロック・ホームズの世界」第9章 引用の出典 1.聖書からの引用)
「かつてあったことは、これからもあり、かつて起こったことは、これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない」(旧約聖書「伝道者の書」第1章9節)からの引用であるとされています。四四 (二三九 150)
15) 実際何をしたかが問題ではないのさ
(引用:「シャーロック・ホームズの世界」第9章 引用の出典 1.聖書からの引用)
「日の下で、どんなに苦労しても、それが人の何の益になろう」(旧約聖書「伝道者の書」第1章3節)を踏まえたものとされています。一七一 (三〇二 375)
もちろん両書簡の作者に議論はあるが、ここで言いたいのは『伝道者の書と雅歌は、伝統的におなじカテゴリで受け取られ、読み継がれている書簡である』ということだ。
ドイルが聖書に詳しいことは知られている。カトリック嫌いの心霊主義者ではあったが、無神論者ではなかったし、下手をするとどんなキリスト教徒よりも『神』という大いなる存在に向き合ったのだろうと思わせるフシがある。『聖書』というものが発する文脈にそれなりに距離を置きながらも活用する、というのはいくらでもやっただろうと想像できる。
【参考】
→「シャーロック・ホームズの世界」聖書からの引用
→文学に表れたキリスト教-コナン・ドイルの場合 田中喜芳(客員研究員)
緋色が罪の比喩に使われる文化は西欧圏の文化として”ある”話-「緋文字」研究より

17世紀のピューリタン社会における律法主義と罪・神の赦しという題材の物語のタイトルには「緋文字(The Scarlet Letter)」とつけられていて、それは文化から浮かび上がってきたものではないか?といった論文もある
『緋文字』(ひもんじ、英: The Scarlet Letter)は、ナサニエル・ホーソーンによって執筆され、1850年に出版されたアメリカ合衆国のゴシック・ロマンス小説であり、多くの場合ホーソーンの代表作であると考えられている。17世紀のニューイングランド(主にボストン)のピューリタン社会を舞台に、姦通の罪を犯した後に出産し、その父親の名を明かすことを拒み、悔恨と尊厳の内に新しい人生を打ち建てようと努力する女性ヘスター・プリン(英語版)の物語を描いている。この物語を通じて、ホーソーンは神の赦しと律法主義、罪悪についての問題を模索している。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2022年6月19日 日本時間13:50分)
わたしが抱く疑問は、この変化が話して感覚レベルにだけ限定されるのか、と言うことなのだ。語り手の意識の深みから浮かび上がってきた「緋色」「文字」は文化のレベルにも接触するのではなかろうか。二つの単語は、聖書において極めて含蓄の深い言葉である。聖書において「緋色」は罪を連想させる言葉である事は、旧約のイザヤ書(1:18)にある通りである。しかし語り手の通りこの言葉がよぎったのは、黙示録の次の箇所を連想したためであろう。
(松阪 仁伺『緋文字』と律法)
(そして松阪氏はヨハネの黙示録17章にて、「大淫婦」が緋色の衣をまとっていることについて言及する)
▽イザヤ書ほか
イザヤ1章18節の「たとい、あなたがたの罪が緋のように赤くても、雪のように白くなり、たとい、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。」と同義的並行法を用いながら、憎むべき罪の色を「緋色、深紅色」にたとえています。
(引用:詩22篇の修辞(2) 「虫けら」という暗喩ー牧師の書斎)
詩篇の22篇6節にある「虫けら」も、一見弱く、惨めな姿ですが、この虫が幕屋で用いる緋色の撚り糸の染料となる虫を意味しています。もちろん、この虫を押しつぶして殺すことによって緋色の色素を取り出すのです。いつまでも色あせることのない緋色の染料。緋色の衣服は非常に高価なものであり、お金持ちや貴人たちだけがそれを着ることができたようです。モルデカイやダニエルも「緋色のマント」をまとったことが聖書に記されています。新改訳では「紫の衣」訳されています。
(同上)
「緋色」とは本来「虫の輝き」を意味します。メシアを予告する「わたしは虫けらです。」というたとえは、メシアなるイエス・キリストが押しつぶされて死ななければならない存在であること、しかもそれは私たちが栄光を与えられるためでした。私たちの輝かしい真っ白な救いの衣は、イエスの流された血潮によって、つまり主の死と苦難の結果として与えられたものなのです。
(同上)
▽ヨハネの黙示録
それから、七つの鉢を持つ七人の御使のひとりがきて、わたしに語って言った、「さあ、きなさい。多くの水の上にすわっている大淫婦に対するさばきを、見せよう。
(ヨハネの黙示録17章1~6節)
17:2地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの女の姦淫のぶどう酒に酔いしれている」。
17:3御使は、わたしを御霊に感じたまま、荒野へ連れて行った。わたしは、そこでひとりの女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚すかずかずの名でおおわれ、また、それに七つの頭と十の角とがあった。
17:4この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の姦淫の汚れとで満ちている金の杯を手に持ち、
17:5その額には、一つの名がしるされていた。それは奥義であって、「大いなるバビロン、淫婦どもと地の憎むべきものらとの母」というのであった。
17:6わたしは、この女が聖徒の血とイエスの証人の血に酔いしれているのを見た。この女を見た時、わたしは非常に驚きあやしんだ。
→「緋文字」ナサニエル・ホーソーン(松岡正剛の千夜千冊)
ドイルの霊と邂逅したら謝らないといけない案件
…もうこれはつまり

ハヤシライスを開発したのはウチのビストロなんです
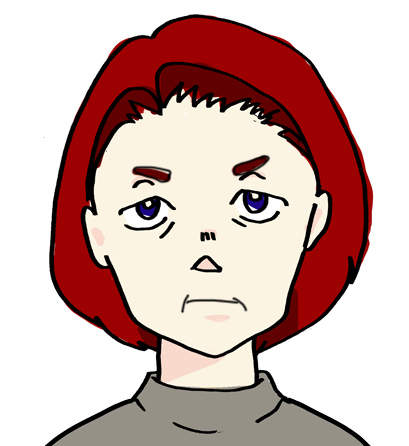
いえ、ウチです
みたいな話なんだな、という所感である(例が近代的すぎるか…?)。まあ正直タイトルに使われる単語の由来なんてのは意味が重なっているほど楽しい&作家の語彙センスへの評価も高くなるもの…と思う。
(これは「Study」を『習作』にするか『研究』にするか『エチュード』にするか、という話にも適応できるかもしれないが…)
当然のことながら、人間と言うのは宇宙の中に独立して存在しているワケではないので、本人が意図している・していないにも関わらず表層として浮かび上がってくること、それが作品の妙味となること、などもいくらでもある(ましてやドイルは心霊主義者だし…?)。
この辺への言及記事が少ないのも「緋色(赤)」が罪、殺人というイメージと結びつくというのは日本語文化圏とっても了解可能だからなのだろうと思う。
▽「緋色」と『罪』の比喩文化はこちらでも言及
アーサー・コナン・ドイルも『こんな部分でやんややんや言わずに俺の書いた歴史小説を読んでくれ』と思っているかもしれない。この先ドイルの霊と邂逅することがあったら謝罪案件である。
一応、「コナン・ドイルの”緋色”、雅歌由来説」が強力でなくなったにもかかわらず、この記事を取り下げずに
補足記事を出すことで事をすませようとしたことへの筆者なりの言い訳を述べたい。
というのは、明確に『雅歌』との関連は断言できずとも、関連しているのでは…と考察されていた『遊女ラハブ』も『雅歌』の話も、筆者にとってどちらも個人的に心を寄せている箇所だったから、でもある。
(※)『遊女ラハブ』と『雅歌』への筆者の心の寄せ方について…聖書の神というのは旧約聖書(タナッハ)の時点では「イスラエル民族の限定的な神」としての印象が強いが、遊女ラハブやその周辺の描写からは、「聖書の神は異邦人の神にもなりうること」を示している、とキリスト教の伝統にはそういう読み方がある。また、ラハブの血筋からはのちにキリストとなるイエスが産まれる。ラハブの職業「遊女」は同時もさげすまれた職業であると認識することができるのだが、神はそういった社会的においやられた存在を用いる、それも果てしない時代を跨いで、という幾重にも折り重なった価値観を示す存在であり、筆者はこのラハブの話のまわりがかなり好きなのである(オタク特有の早口)。
また、『雅歌』は雅歌で、聖書の謎と豊潤さをまさしく体現しているような存在で、その謎めいた感じが「神の言葉というのはかくも人間の手にあまる、しかしそれは確実に”愛”と呼べそうなーそれも、男女の肉体関係を含む卑近な”愛”―を肯定するものである、というそういう感じが好きなのである(オタク特有の早口)。
聖書を…とりわけ筆者が好むような角度から聖書を紹介すると『たぶん死ぬまで解けない謎について考えるの、エモいよね』みたいな切り口になってしまうので、推理小説愛好をする方々には少々すわりが悪いかもしれないが、もし気が向いたならこの世界の「謎」を堪能する手段のひとつに『聖書』という存在を介在させる選択肢を考えて下されば…幸いである。
(とはいえ、筆者は「生きている間にこの謎は自分には明かされないんだろうなぁ」と思っていたことが数年のスパンを経て明かされることもいくつか体験しており、「じゃあなんでその数年待てたんや」となるとそれはもう自称:この世界最強の霊であるブラハム宗教の神がこの世界の神だと思っているから…という、まさしく「信仰」のなせる業だったなと思う…のもあるので…世界のデカい謎を知りたいと渇望する場合には、それが「私」に明かされることも願っていい、とは思っている…。それは、このコラムで扱ったような、コナンドイルが「緋色」をどこまで意識して命名したか?という謎も含めて、である。)

シャーロック・ホームズと99人の賢者

シャーロツク・ホームズ大事典

シャーロック・ホームズの推理博物館 (河出文庫)

