「おもしれ―女」がもはやミーム化してどれくらい経つのでしょうか。少なくとも平成という時代のなかで醸造されていったコード、だとは認識していますが。
おもしれー女とは、少女漫画に出てくる学園中の女生徒をハーレムのごとく侍らせている現実ではなかなかありえないレベルの俺様系イケメンが全く自分になびかない女主人公に興味を持って軽い気持ちでキスをしようとしたところ頬を引っ叩かれた上に「誰でもあんたのこと簡単に好きになるなんて思うな!」的な言葉をぶつけられて後ろ姿を見送りながら自分の頬をさすって独り言的につぶやくセリフである。
(引用:ニコニコ大百科「おもしれー女」項2022年6月8日13:38時点)
あらゆる女にモテている俺様系イケメンになびかないがゆえに面白がられて恋される女の子を指すこの言葉。イケメンが彼女に、「おもしれー女じゃん」と言うイメージとともに広まってきました。少女マンガや乙女ゲームなどに確かにあるなと思う展開ですが、具体的にあの作品が発祥、とはなかなか思いつきません。
(引用:「おもしれー女」について考える あなたの「おもしれー女」はどこから? ―コミックナタリー)

「おもしれ―女」の発生源や歴史などは別の媒体にまかせて、この【いつかみ聖書解説】では
「おもしれ―女」の構造を抽象化してみることで、創作や現実への適応度を上げる
ことができると思ったので、それをやっていこうと思います。また、その抽象化の過程で
いわゆる『聖書』と呼ばれているキリスト教の聖典からも「俺はおもしれ―女を祝福するぞ」という世界観が提示されている。
とも思ったので、そのへんもしたためます。
一般的(その物語において基本的)に忌避されている(王道とみなされていない)行為によって、その物語に於いて重要な存在(物語の場合は〈一人のキャラクター〉にその役割が投影されている場合が多い)からかえって目をかけられる/祝福される構造のこと。
…大胆に要約すると…
秩序の反転による慰め、回復、祝福(救済)。
↓
聖書には「おもしれ―女」の物語もあるし、「秩序反転による慰め、回復、祝福(救済)」は聖書全体の構造とも同期している。
この抽象化がしっくりこない方は、このコラムをこれ以上読んでも苦痛かと思いますのでブラウザバックを推奨します。また、「おもしれー女」の物語を創作物に反映させたいという気持ちでこのコラムを開いた方も、ここまで抽象化したら、正直あとは適応し放題だと思いますので、ここで帰ってもOKです。あなたの想像力の仕事の祝福を祈ります。
筆者は、『宗教』は人間の認知の仕組み介入する機能がつねに含まれる営みだと考えており、とりわけキリスト教徒たちが『聖書』と呼ぶシロモノについて(評価はどうあれ)その影響力を注視する立場に立ちます(それは内容についてもそうですが、シンプルに世界のシェア度と歴史における立ち位置からそう考えています)。ですので、その前提を共有できない方には不要なコラムであると思います。
目次
「秩序の反転による慰め、回復、祝福」の抽象化は適切か?
まずは
一般的(その物語において基本的)に忌避されている(王道とみなされていない)行為によって、その物語に於いて重要な存在(物語の場合は〈一人のキャラクター〉にその役割が投影されている場合が多い)からかえって目をかけられる/祝福される構造のこと。
…大胆に要約すると…
秩序の反転による慰め、回復、祝福(救済)。
とすることへの、筆者なりの必然性をカンタンに解説していきます。
- J・R・Rトールキン(現代ファンタジーの源流とされる作家のひとり)の言っている『ユーカタストロフ(幸せな大詰め/佳い破局)』(妖精物語の究極機能)はこの構造を含めた物語構造の事を指していると思ったから。(※1)
- 「秩序の反転による祝福」がふつうにキリスト教の特徴だと筆者は思っているから(※2)。
- これくらいの解像度にすると、『聖書』(一応世界で一番読まれている書物)のなかでもとりわけ『エステル記』に「面白さ」を感じる人が多い理由が説明できるから。
(※1)筆者はトールキン作品のこの現代日本への影響力も注視する立場です。
(※2)筆者は『キリスト教』の影響下で紡がれてきた文化の、現代日本への影響力を「未知数ではあれど、無視できない程度にはある」とする立場です。

とりあえずは、「ここまでの抽象化に一理感じる」という方は読み進めてくだされば幸いです。
これは今まで摂取してきたマンガ・アニメなどの物語文脈を踏まえた読み手の「カン」みたいな感じなので、言語化していくのには時間がかかるし本論とはズレるので、
詳細な解説についてはそのうち詰めていきたいと思います。
「ユーカタストロフ」についてはコチラのコラムを読んでいただければと思います。
▽こんなんも書きました
 【ダミアニャ考察】「成長if/未来捏造は苦手」だったが道明寺司文脈とおもしれー女構造の深読みで擁護派に転んだオタクの思索
【ダミアニャ考察】「成長if/未来捏造は苦手」だったが道明寺司文脈とおもしれー女構造の深読みで擁護派に転んだオタクの思索
聖書に描かれたわかりやすい「おもしれ―女」エピソードを持つエステル
それでは、次に『聖書』にある、非常にわかりやすい「おもしれ―女」が活躍するエピソードとして『エステル記』を紹介します。
『エステル記』を知らない方は、一度読んでみるか、以下の動画でざっくり知識を得てから、このコラムで詳細に触れる部分についてだけ読んでみるのがいいと思います。全部読んだとしても10章なので、ちょっと集中すれば読めると思います。
→ブラウザでお手軽に読むならYouVersion
→聴くドラマ聖書なら、オーディオブック的に摂取できます。
→リビングバイブル

これがどうキリスト教の信仰に関係してるの?という不思議さがある
と思う方も少なくないと思いますので、理解の助けになる程度にカンタンに紹介します。
この書は、雅歌と同様に、神名が一度も出てこない、新約聖書にも引用されない、モーセの律法に規定されていないプリムの祭りが命じられているなどから、正典性が問題視された。実際、クムラン宗団が所有していたとされる死海写本の中に、その断片すらも見つからないなど、色々と問題視された書でもある。しかし、神名を用いずに、人間の世俗的な営みの中に、神の見えざる手が働き、神のみこころが実現されていくことを確認させる書である。
(引用:人生が100倍楽しくなる、パスターまことの聖書通読一日一生5(旧約聖書 新約聖書 聖書通読ブログ))
↑は、いちプロテスタント牧師のブログからの引用です。ここに書かれていることは私が今まで過ごしてきたキリスト教の共同体(福音派と呼ばれる、ホーリネス系統のプロテスタント)のなかでも、『エステル記』の説明のときはだいたいこういった前提を話された記憶がありましたし、いくつか読んだエステル記にまつわる論文の中にもこういった認識があったので、とりあえず掲載します。
以前作ったツイートです。デフォルメされている=作り手の解釈が強く反映されている コンテンツですが、少なくとも現代日本を生きるイチプロテスタントキリスト教徒は『エステル記』をこういったデフォルメができるものだとも受け取っている…という点が、解釈の補助線のひとつにはなると思ったので挙げます。
次回予告風で学ぶエステル記 放送開始前CMVer pic.twitter.com/YMV9vYeTn3
— いつかみ聖書解説@低浮上 (@LampMate) March 13, 2021

自己防衛のためだからってそこまでしてエエのん…?

エステル、ハマン一族に対してオーバーキルでは…?
『エステル記』を読んでいると、こういった感想もまた抱かれる方がほとんどだと思います。そこに目が行くと手放しで「おもしろい」とは言えない物語ではあるかと思います。とはいえ、どうもそれは古代教父や原始のキリスト教徒も同じだったもよう。
「エステル記」の受容に関しては、ユダヤ人とキリスト教徒の間には、長らく大きな隔たりがあった(22)。恐怖時代のおよそ七世紀間、キリスト教徒による「エステル記」の注釈は書かれてこなかった。ディアスポラのユダヤ人の民俗的勝利を記念するこの書は、非ユダヤ人に対する粗野で野蛮な行為の認可など異教じみた悪行や性質が内包されるがゆえに、多くのキリスト教徒にとって共感し難いものであった。しかし9世紀以降、キリスト教の文脈において、ヘブライ語聖書を新約聖書の出来事や刑事の予示とする予型論的解釈から、エステルは慈愛のモデルとして、マリアの元型ともみなされていく(23)。さらに、ハマンみずから吊るされることになる木の絞首台は、磔刑の十字架を予示するものとされるのである(24)。
(引用:『カド・ハ・ケマフ』におけるエステルの「食卓」―慈悲と救済のとりなし手 蓼沼理絵子 )
これについては、一神教の精神的土壌としての
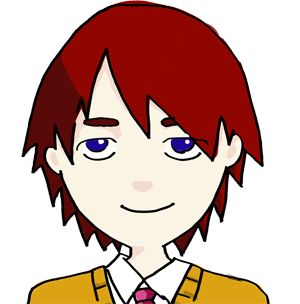
ちょっと僕たちには信じられないけど、そもそも神の考えることなんて人間にはわからないし…
みたいな世界観を了承していただき(「理解」「共感」ではないです、念のため。)、「この人たちはそういう世界観の生き物なんだな」と認識していただければ、とりあえずこのコラムを読むにあたっての問題はクリアできるのではないかな…と思います。

『神はこの物語を通して我々人間に何を問おうとしているのか?』という思索の営みがキリスト教及び一神教の精神的土壌である、というのは言えると思います。
神が我々に何を問おうとしているのかを色々何世紀にも渡って考えては「ココまでは言ってええんちゃうん」「いやいや、それは違うんちゃうん」みたいな攻防戦を繰り返しながら、キリスト教というものは世界に散らばっていっている…というのはご了承いただけるといいのかな…と思います。

『エステル記』が歴史的な出来事をどこまで反映して記録しているのか、というのも議論がわかれるとこですしな。
『聖書の神が全知全能である、善である」という前提を共有する必要がない人がほとんどだと思うので、しっくりこないかもしれませんが、どうしても無理な場合はお帰りくださいませ…。
①『エステル記』第1の「おもしれ―女」現象を解剖~妃へ召し上げられる際のエピソード~
6 さて首都スサにひとりのユダヤ人がいた。名をモルデカイといい、キシのひこ、シメイの孫、ヤイルの子で、ベニヤミンびとであった。
彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕えていったユダの王エコニヤと共に捕えられていった捕虜のひとりで、エルサレムから捕え移された者である。
7 彼はそのおじの娘ハダッサすなわちエステルを養い育てた。彼女には父も母もなかったからである。このおとめは美しく、かわいらしかったが、その父母の死後、モルデカイは彼女を引きとって自分の娘としたのである。
8 王の命令と詔が伝えられ、多くのおとめが首都スサに集められて、ヘガイの管理のもとにおかれたとき、エステルもまた王宮に携え行かれ、婦人をつかさどるヘガイの管理のもとにおかれた。
9 このおとめはヘガイの心にかなって、そのいつくしみを得た。すなわちヘガイはすみやかに彼女に化粧の品々および食物の分け前を与え、また宮中から七人のすぐれた侍女を選んで彼女に付き添わせ、彼女とその侍女たちを婦人の居室のうちの最も良い所に移した。
10 エステルは自分の民のことをも、自分の同族のことをも人に知らせなかった。モルデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。
11 モルデカイはエステルの様子および彼女がどうしているかを知ろうと、毎日婦人の居室の庭の前を歩いた。
12 おとめたちはおのおの婦人のための規定にしたがって十二か月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであった。これは彼らの化粧の期間として、没薬の油を用いること六か月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること六か月が定められていたからである。
13 こうしておとめは王の所へ行くのであった。そしておとめが婦人の居室を出て王宮へ行く時には、すべてその望む物が与えられた。
14 そして夕方行って、あくる朝第二の婦人の居室に帰り、そばめたちをつかさどる王の侍従シャシガズの管理に移された。王がその女を喜び、名ざして召すのでなければ、再び王の所へ行くことはなかった。
15 さてモルデカイのおじアビハイルの娘、すなわちモルデカイが引きとって自分の娘としたエステルが王の所へ行く順番となったが、彼女は婦人をつかさどる王の侍従ヘガイが勧めた物のほか何をも求めなかった。エステルはすべて彼女を見る者に喜ばれた。
16 エステルがアハシュエロス王に召されて王宮へ行ったのは、その治世の第七年の十月、すなわちテベテの月であった。
17 王はすべての婦人にまさってエステルを愛したので、彼女はすべての処女にまさって王の前に恵みといつくしみとを得た。王はついに王妃の冠を彼女の頭にいただかせ、ワシテに代って王妃とした。
いわゆる「教訓」的なものを汲み取ろうとすると
「無欲さが功を奏して王妃の位を得た」
↓
「損して得とれ」
みたいにも取れるお話だとは思いますが、その欲求をちょっと抑えて、最初に述べたように
「『贈り物の遠慮』という、普通はやらない行為でかえって目を掛けられるようになった(※)」
くらいまで抽象化してみることとします。
(※)本文には「彼女は婦人をつかさどる王の侍従ヘガイが勧めた物のほか何をも求めなかった。エステルはすべて彼女を見る者に喜ばれた。」としか書かれてないので、「無欲さが功を奏した」という読み方も解釈の一種なのですが、逆に今から②で話す構造と合わせて物語として考えると、こういう解釈はアリなんじゃないの…という話をしていきます。
②『エステル記』第2の「おもしれ―女」現象を解剖~死刑覚悟の王への直談判~
「死ななければならないのなら、死にます」
というエステルの台詞が非常に印象的なので、このへんのくだりをいわゆる「クライマックス」と認識する方が多いと思います。
ただ、全体を通して見てみると、エステルは2度目の『贈り物の遠慮』を行っていることがわかります。
序盤で行ったことがクライマックスにも行われた、ということはこのストーリーにとってそれが重要なファクターを占めている、ととることはできると思います。
基本的には忌避されている行為が、成功(祝福)につながった
それらが2度にわたって行われたと読み取れる…のではないでしょうか。
最終的に「おもしれ―女」と『エステル記』はシンクロします。」(※)
(※)「最終的に子安とZAZELはシンクロします」のオマージュ

「物語のはじめとクライマックス」に『秩序の反転による祝福』って構造がある
→「それがこのストーリーのメッセージのひとつと考えていいんじゃない?」って言いたいわけね。
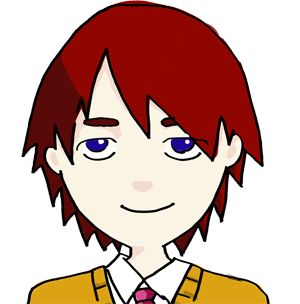
「千夜一夜物語」シエラザード(シェヘラザード)=エステル説っていうのも不人気ながらあるらしいよ(※)出典確認してきます

シエラザードが広い意味で「おもしれ―女」に入るというのはわかりみが深い気がする…
構造を抽出して物語を読むことが好きな筆者としてはこの辺の重なりは世界の面白さを増すばかりで何の問題もないな…と思います。
最終的に「おもしれー女」と『聖書』はシンクロします。
と、ここまでおもしれ―女=反転する秩序による祝福→という話をしてきましたが、聖書は全体的にそういう話がちりばめられている…と思います。
ユダヤ教とキリスト教がともに歴史的に主たる関心を抱いていたことは、悪魔学ではなく、未来における大逆転(culbute générale)への期待である。正しい信仰を持っている、あるいは正しい心構えでいる自分たちが、今大きな力を持っている敵が無力になることによりトップに立つ時の、いわば再認の場面のことである。この逆転のもっとも単純なものは「エステル記」にある。モルデカイを吊るすために作った絞首台でハマンが絞められる。そして彼の一派が皆殺しに合う。しかし、このきわめて非妥協的な書でさえも、世俗権力と衝突するよりは妥協しようとするユダヤ教の一般的傾向を反映している。ペルシャの王は「ダニエル書」の中のネブカドネザルやダリウスのように、彼の王国をそのまま所有している。すでに見たように、パウロは世俗権力への恭順を奨励した。しかし、全世界が正しい信仰で結ばれるまで何事もうまくいかないという全般的な感情は、キリスト教にもイスラム教にも、そして今日のマルクス主義にも残っている。
(大いなる体系pp.164-165)
(マーカーは筆者によるもの)
筆者が聖書を読んでいてえも言われぬエモさを感じるのは、仕組みはどうあれそれが至るところにちりばめられていている、という感触があります。
- 聖母マリア
- 末子成功譚的な構造
- 「後のものが先になる」垂訓
- 食卓のくずもいただきますの婦人
- 長血の女
その最高峰がイエスの十字架の死と復活に(仕組みはどうあれ)現われている…というのがトールキンが言ってる「ユーカタストロフ」であるとか、ルイスが『Myth Became Fact』で語ってることとかを統合するとそういうことになるんだと思っています。
細かくはこのコラムでは割愛します。
『キリスト教』『聖書』というと、一人ひとり違うものを観ている可能性もあるので、そこは念頭において頂けると幸いですが、少なくとも著者(現代日本人キリスト教徒)が
あぁ~聖書くっそエモい、くっそエモい(大事なことなので2回言いました)
と思う際に筆者が何を感じているかということを慎重にたぐっていった結果、ではあるし、
細いながらもプロテスタント福音派と呼ばれるキリスト教の共同体につながって、「他の人は聖書からどういった感想を持つのか見聞きしていると、言語化はされてなくてもそういうところに感動を覚えている人もいるっぽいな」というのを肌で感じた結果のアウトプットではあります。
(もちろん言語化しきれていないほかの要素が多分にあるとは思いますが)
こういうのを物語論的読み方のひとつ、と言うのかもしれないが、少なくとも現代プロテスタントの共同体につらなる身としてはこういう読み方を言語化していく試みはそんなに盛況ではない。
筆者はノースロップ・フライの著作を読んだときに「そうそうそうそう!こういうのがほしかったんだ!」と思ったものだが、筆者がキリスト教なるものと出会ってから足掛け8年?くらい後である。もっと早く「こういう読み方がある」と知りたかったので、こういうコラムを書いているのはそういう理由もあります。
だからここに書くことにする。
あなたが「おもしれ―女」を描きたくてその構造を考えている人なのか、自分自身が「おもしれ―女」になりたいのか、はたまた単に知識欲が高じて覗かれたのかはこちらはわかりませんが、
いずれの道にも『聖書』というシロモノへの読みを人生の選択肢に入れるのはいかがでしょう?というお話でした。
キリスト教がかなり不合理で、いわゆる「賢くはない人たち」向けの宗教であったにもかかわらず歴史のある一地点で爆増し(、そこからは頭のいい人たちにもいろいろと受けて練られて考えられて受容されたり反発されたりしながら混淆して分かれてここまできているわけですが、)たのは「イエスという存在が提示した物語の強度」は必ず言えると思います。つまりそのへんを読みといていく事は人間の心に迫る物語構造の秘訣が何かしらあるのだと思います、
また、自身が「おもしれ―女」になるという願望に関しては、まずもって現代日本の王道の文脈から外れるという行為として「一神教知識を増やす」ことはそれだけでそれになる&仮にその信仰観を身に着けることは「我ー汝(自分と神の関係)」という関係性の追求がかなり大きなポイントになってきますので、となると「周囲に流されにくい」という、おもしれ―女が一般的に持っている特徴のひとつが自然と身につく可能性がある、という点などにおいて「あり」なんじゃないのかな…と思います。
第二次世界大戦中、日本政府はさまざまな思想を取り締まり、多くの宗教団体もその対象としました。キリスト教会の多くは政府側につくことに成功しましたが、それができずに留置所に拘置されてしまったり、そのまま獄死してしまったキリスト教牧師や信徒たちがいたグループがあります。(※「ホーリネス弾圧」)
その記録の中に、まるで「おもしれ―女」的振る舞いをして、特別高等警察から驚かれた女性牧師の記録があったので、ちょっと紹介してみます。
…特高の二人は、「僕たちはあなたを調べるようになってから夜十二時前に寝たことがない、お陰で聖書を調べなければならない。それもよいでしょう。僕たちが求道者になったり父親になったり親友になったり、実は君との交流によって考えさせるられることがいろいろあるのだよ。
足利へ君を迎えに行った時、あの拘引状を差し出しても顔色一つ変えず、朝食をいっぱい食べ、またおかわりして二杯食べていたが、これには実に驚いたよ。
今まで多くの人に拘引状を差し出したが、あのような大胆な人には会ったことがない。若い小娘の君が平然として僕たちについてきた。僕たちの生涯でこういう人は初めてであった。それも君に言わせれば信仰のしからしむ所だと言いたいのでしょうが」。
(新教出版「ホーリネス・バンドの軌跡 リバイバルとキリスト教弾圧 ホーリネス・バンド弾圧史刊行会編」『男の牧師と思われて』より井上馨の証言p.270)
 【ダミアニャ考察】「成長if/未来捏造は苦手」だったが道明寺司文脈とおもしれー女構造の深読みで擁護派に転んだオタクの思索
【ダミアニャ考察】「成長if/未来捏造は苦手」だったが道明寺司文脈とおもしれー女構造の深読みで擁護派に転んだオタクの思索
▽キリストの物語が「強度ある物語」だったんじゃないかと話すVtuber
こちらで話されているVtuber足袋田クミさんは「神はいないと思っているが聖書を読むのはやめられない」という世界観の方なので、キリスト教信仰を持ってない方も安心して観れる動画だと思います。

