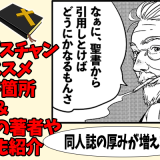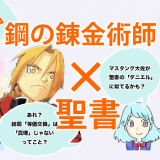全国の殺生丸さま尊みクラスタさま、お元気でしょうか。

私 は 元 気 で す !
この度「半妖の夜叉姫」の瘴気にあてられて、かつての殺生丸さまへの想いをぶり返してしまった方や、この度殺生丸さまへの想いが芽吹いてしまった方など、さまざまな背景の方がいらっしゃることと思います。
今日は、そんなみなさまに「二次創作に引用・コスプレ写真に添えるなどするとカンタンに深みが出せる古典ポエム『雅歌』」を紹介したいと思います!

『雅歌』は、旧約聖書の書簡のひとつでございます。聖書の書簡のなかでも「コレ、聖書に入ってていいの?」と思えることに定評のある、ちょっとアダルトなポエム書簡でございます。くわしくは追って解説いたしますな…。
▼みんなの「殺生丸さま」「殺生丸様」ツイート
ということで、「同人誌をアツくする聖書入門~殺生丸の女たちに捧ぐ~」開幕!
※このページは二次創作による「同人活動」の文化をベースに語られています。苦手な方はUターンをおススメします※
・
・
・

・
・
・
目次
『雅歌(がか)』(旧約聖書)とは

『雅歌』(がか、ヘブライ語: שיר השירים Šīr-hašŠīrīm シール・ハッ=シーリーム、独: Hohes Lied、英: Song of Songs あるいは the Song of Solomon)はヘブライ聖書の中の一編。
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「雅歌」項より』
男女の恋の歌であり、ユダヤ教では「諸書」のうちに入る。キリスト教では伝統的に預言書の前に置かれる。恋愛と男女の賛美を歌い上げる詩であるため、扱いをめぐって古くから議論が絶えなかったが、さまざまな経緯を経て正典におさめられた。キリスト教の置換神学においては比喩的に解釈して「キリストと教会の関係」を歌う歌であるという解釈がされてきた。ある意味、異色の作品である。
1:1に「ソロモンの雅歌」として、ソロモン王の作であるとされる。内容は花嫁と花婿の詩、娘たちの合唱などが組み合わされている。
「雅歌は聖書の中でもきわめてユニークな書です。8章にわたる愛のうたから成り立っていて、導入と結論があるほかは構成らしい構成はありません。というのも、これは詩集だからです。細かく分析するのではなく、全体を通して読み、ただ味わうためのものです。」
(聖書プロジェクト BibleProject – Japanese「雅歌 Song of Songs【概観】」冒頭より)
書かれた目的:花婿(ソロモン王)と花嫁の愛について語り、結婚の神聖さを確認し、ご自身の民に対する神の愛を描く。
記者:ソロモン
執筆年代:おそらくソロモン治世の始め
舞台/背景:イスラエル――シュラムの女の庭とソロモンの宮殿
おもな登場人物:ソロモン王、シュラムの女、友人たち
(参考:いのちのことば社「バイブルナビ」雅歌項)
まとめると
・詩なので引用しやすい
・「高貴な男性」を想定するとぴったり
・古典から引用すると、手軽にコンテンツに深みを出せる
・マイナーなので差別化しやすい
・仏教系は恋愛には向かない
【参考】
・ソロモン王は古代イスラエルの最盛期を築いたとされる王です。戦国最強の殺生丸さまに重なりますね!
・聖書は世界で一番読まれている本であり、さまざまな文学作品の元ネタにもなっています。
・とはいえやはり古典扱いされることが多いうえ、雅歌はクリスチャンのなかでもあまり読まれない書簡に入る印象なのでかぶりの心配がありません。
・仏教に関しては以下を参照
→仏教の「縁起」を理解すれば、失恋の傷は秒で癒える!かもしれない(稲田ズイキ著「罰当たりなほどにユルくてポップな仏教トーク)
→四苦八苦(一切皆苦)| 仏教が説く8つの苦とは(ハスノハーお坊さんが答えるお悩み相談サイト)
といった特徴があり、殺生丸さまの女たちに引用・挿入していただきたい書簡なのであります!
「雅歌」はこんなかんじ
※これらはすべてパブリックドメインになっている 「口語訳聖書」「文語訳聖書」を使用していますので、コピペOKです。
あなたのあとについて、行かせてください。わたしたちは急いでまいりましょう。王はわたしをそのへやに連れて行かれた。わたしたちは、あなたによって喜び楽しみ、ぶどう酒にまさって、あなたの愛をほめたたえます。おとめたちは真心をもってあなたを愛します。(口語訳)
われを引きたまへ われら汝にしたがひて走らん 王われをたづさへてその後宮にいれたまへり 我らは汝によりて歡び樂しみ酒よりも勝りてなんぢの愛をほめたたふ 彼らは直きこころをもて汝を愛す(雅歌1章4節)
干ぶどうをもって、わたしに力をつけ、りんごをもって、わたしに元気をつけてください。わたしは愛のために病みわずらっているのです。 どうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、右の手がわたしを抱いてくれるように。(口語訳)
請ふ なんぢら乾葡萄をもてわが力をおぎなへ 林檎をもて我に力をつけ。 我は愛によりて疾わづらふ。彼が左の手はわが頭の下にあり その右の手をもて我を抱く。(雅歌2章5~6節)
あなたのくちびるは紅の糸のようで、その口は愛らしい。あなたのほおは顔おおいのうしろにあって、ざくろの片われのようだ。(口語訳)
なんぢの唇は紅色の線維のごとく その口は美はし なんぢの頬は面帕のうしろにありて石榴の半片に似たり(雅歌4章3節)
わが妹、わが花嫁よ、わたしはわが園にはいって、わが没薬と香料とを集め、わが蜜蜂の巣と、蜜とを食べ、わがぶどう酒と乳とを飲む。友らよ、食らえ、飲め、愛する人々よ、大いに飲め。
わたしは眠っていたが、心はさめていた。聞きなさい、わが愛する者が戸をたたいている。「わが妹、わが愛する者、わがはと、わが全き者よ、あけてください。わたしの頭は露でぬれ、わたしの髪の毛は夜露でぬれている」と言う。
わたしはすでに着物を脱いだ、どうしてまた着られようか。すでに足を洗った、どうしてまた、よごせようか (口語訳)
わが妹わがはなよめよ 我はわが園にいり わが沒藥と薫物とを採り わが蜜房と蜜とを食ひ わが酒とわが乳とを飮り わが伴侶等よ 請ふ食へ わが愛する人々よ 請ふ飮あけよ。
われは睡りたれどもわが心は醒ゐたり 時にわが愛する者の聲あり 即はち門をたたきていふ わが妹わが佳耦 わが鴿 わが完きものよ われのために開け わが首には露滿ち わが髪の毛には夜の點滴みてりと。
われすでにわが衣服を脱り いかでまた着るべき 已にわが足をあらへり いかでまた汚すべき。(雅歌5章1~3節)

殺生丸→りん・神楽・夢女子
りん・神楽・夢女子→殺生丸
でも使えそうな脅威の汎用性では…?

「現代の歌」に想いを載せるのも佳いですが、古典を引用するとまたひとあじ違った深みが出せる…と、この「じい」などは思いますな。
ということで、『雅歌』は殺生丸さまの女たちにぜひ使ってほしい書簡なのであります!!(大事なことなので2回言いました)
▼こっちもよろしく
 聖書からの名言引用は悪手?代わりにキリスト教世界観作家とか哲学者たちをまとめる~力尽きた、ここからたぐって~
聖書からの名言引用は悪手?代わりにキリスト教世界観作家とか哲学者たちをまとめる~力尽きた、ここからたぐって~
 【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】
【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】
時代考証的なものはどやねん
「犬夜叉」自体、あまり時代考証しながら作られている漫画でもないので、そのへんあんまり気にしなくていいかなーとは思います。
一応、日本でキリスト教が入ってきたのは1549年の戦国時代だということを踏まえると、戦国時代に生きる存在が旧約聖書を知っていたとしてもとくに問題はないと思われます。
→日本のキリスト教史(フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)
聖書を一般の人が読むことはなかったかもしれませんが、そこは殺生丸さまなので…。
また、聖書はユダヤ教キリスト教を信じる立場からすると「神の霊感がはたらいている書」と考えらているので、『神の霊感をなにかのタイミングでキャッチできたら思い浮かぶ』こともあるかもしれません、やはり殺生丸さまなので…。
また、厳密にはキリスト教ではないけれどよく似た宗教「景教」は、4世紀ごろには大陸から輸入されていた可能性があります。「景教」はおそらく「キリスト教ネストリウス派」だとされていますが、この派の解釈から推察すると、イエスが生まれる前から存在している旧約聖書の『雅歌』についてはそのまま利用されていただろうなと思います。
ということで、殺生丸さまの女たちは安心して『雅歌』を引用・挿入してくださればと思います。
超絶余談・河合隼男の語る「半妖」の子どもたち
犬夜叉と言えば「半妖」、今回も『半妖の夜叉姫』たちが主人公なので、この「半妖」というキーワードを考えたとき、思い浮かんだ話しをしてみます。
木樵の男が仕事をしていると、鬼が出てきて、あんこ餅が好きかと聞く。男は女房と取り替えてもいいほど好きと答える。そこで、男は鬼のくれたあんこ餅をたらふく食べるが、帰宅すると妻がいないので驚く。
男は妻を探して、一〇年後に「鬼ヶ島」を訪ねる。そこに一〇歳くらいの男の子が居て、体の右半分が鬼、左半分が人間で、自分は「片子」と呼ばれ、父親は鬼の頭で母親は日本人だと告げる。片子の案内で鬼の家に行き、女房に会う。
男は女房を連れて帰ろうとするが、鬼は自分と勝負して勝つなら、と言って、餅食い競争、木切り競争、酒飲み競争をいどむ。すべて片子の助けによって男が勝ち、鬼が酒に酔いつぶれているうちに、三人は舟で逃げ出す。
気づいた鬼は海水を飲み、舟を吸い寄せようとする。このときも片子の知恵で鬼を笑わせ、水を吐き出させたので、三人は無事に日本に帰る。
片子はその後、「鬼子」と呼ばれ誰も相手にしてくれず、日本に居づらくなる。そこで両親に、自分が死ぬと、鬼の方の体を細かく切って串刺しにし、戸口に刺しておくと鬼が怖がって家の中にはいってこないだろう。それでも駄目だったら、目玉めがけて石をぶっつけるように、と言い残して、ケヤキの木のてっぺんから投身自殺をする。
母親は泣き泣き片子の言ったとおりにしておくと、鬼が来て「自分の子どもを串刺しにするとは、日本の女房はひどい奴だ」とくやしがる。そして、裏口にまわって、そこを壊してはいってくるが、片子の両親は石を投げ、鬼は逃げる。
それからというものは、節分には、片子の代わりに田作りを串刺しにして豆を撒くようになった。
(大塚信一著「河合隼雄 物語を生きる」pp.130~131)
→YouTubeで語られているのは、テキストとは違ったタイプの物語です。そのほかエピソードのバリエーションなどはWikipediaなどが参考になるかと思います。
これは実に恐ろしい終末である.(中略)半分鬼であるばかりに,両方の重荷に苦しめられる片子は,日本に長く住めなかった.誰も父親の国に戻ってくれとは頼まなかったし,誰も片子に危害を加えはしなかった.それでも片子は日本人と関係を持つことができなかった.この見えないプレッシャーのために,ついに片子は自殺に追い込まれることになった.鬼が,「自分の子どもを串刺しにするとは,日本の女は恐ろしい」と言ったのは極めて意味深い.それは日本の女性性が残酷な側面を持っていることを示している.それらは自らの肉と血を拒絶して,強い男性性によって侵略されることから自らを守ろうとしているのである.
(引用:河合隼男著「日本神話と心の構造ー河合隼男ユング派分析資格審査論文ー」日本語訳 pp.237~238)
片子が祖父に自分を殺すように頼んだことも考察に値する.これはグリム童話の「黄金の鳥」のことを想起させる.「黄金の鳥」の話で,主人公はさまざまな方法で助けられる.万事が幸せに終わったように思われた物語の最後において,狐は主人公に自分を殺してくれと頼む.主人公はもちろん気が進まないけれども,狐があまりにも熱心に懇願するので,ついには同意する.狐が殺され,バラバラにされると,輝かしい王子となって生まれ変わる.もし片子の望み通りに,日本人の祖父が片子を殺していたらどうだっただろうか.グリム童話の狐のような突然の変容というのは,片子が半分日本人であるので,起こらなかったように思える.片子に開かれた唯一の道は,自殺することだったのだ.
なんかこのへんも妄想の足しになるかもしれないと思ったので、投げるだけ投げますね。
さて、「犬夜叉」の物語そのものは、宇野常寛氏が『母性のディストピアの物語である』と評してやまないわけですが…
— いつかみ聖書解説、時々、蛇イさん (@LampMate) August 19, 2020
令和の時代、「半妖の夜叉姫」に描かれる片子達のストーリーはどうなるのか。母性のディストピアで生まれた片子たちがどんな物語を紡いでいくんでしょう。https://t.co/mpNpipzX16
▼いつかみ聖書解説~石本伝道師編~