そもそも論…
『グリム童話』を構成する伝承は、ユグノー派(フランス系プロテスタント)の子女・婦人たちをとおして収集されたものであるため、聖書物語のグリム童話への影響をある程度見とおすことができるに違いない。
(引用:「グリム童話に見られる聖書的モティーフ─上方と下方という観点から」堀川敏寛,2022年,)
『グリム童話』とは、複数の語り手によって得られた伝承から形成されたメルヒェンであるため、たとえばドイツという一つの文化圏のみの影響で、グリム童話を語ることができない。メルヒェンには、ゲルマン由来の伝承とユグノー由来のものとが混在している、と考えることがベストであろう。
(引用:「グリム童話に見られる聖書的モティーフ─上方と下方という観点から」堀川敏寛,2022年,p.91)
…というユダヤ思想研究者(?)の論文があるし、当コラムライター自身もド素人ながらそう思う。ただ、一般人が知りたいのはもう少し割り切った話だとも思う。なので、このコラムは

グリム童話と聖書(あるいはキリスト教)との関係を知りたい!(※)

…みたいな人が『初手で知りたい話ってこれくらいの塩梅じゃないかな…』っていう塩梅を当コラムライターが考えて・整理して・まとめるページ
(※)現代日本語圏において「聖書」とみなされているものはおおよそキリスト教界隈の認識による「聖書」であると考えられているのが現実だと感じておりますのでこのように表現しているだけで、当コラムライター自身が〔”聖書”とはキリスト教の聖典を指す用語でしかない〕と考えているわけではありません。
である。聖書・キリスト教まわりになじみが薄い人にも得心しやすいように、それらの解説もできる限り補足する所存ではある。(やってみたけど難しかった。かなり手薄になってるけどご容赦ください)
しかし、要約は解釈と不可分であり、解釈には解釈する主体の思想が入りこむ。
なので、このページに入られた皆さまにおかれましては、このようなどこの馬の骨とも知れない人間の思想に付き合う義理はないはずである。ここで言及していく紹介している書籍や論文を買うなり借りるなりしてご自身で読まれたほうがいいことは先に申し添えておき…
…OKな方のみ読み進めていただければと思う。
…主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて、だれのところへ行きましょう…
目次
「神」が登場するグリム童話~じつにその1/4

グリムメルヒェン集の4分の1に「神」が登場したり言及されたりする
特に魔法メルヒェンは主にハッピーエンド型の形式をしており,神はそれらの話の中では大きな役割を担っている。神が個別の単語で用いられている話,あるいは語り手によって引き合いに出されたり,神の名が告げられたりしている話は 42,神が人間などの実際の姿で此岸の世界に登場する話と合わせると 52話であり,実にグリムメルヒェン集の全200話の4分の1にも及んでいる。
(引用:グリムメルヒェンのモティーフを探る ⑼―グリムメルヒェンにおける神々とキリスト教の神―満足 忍 pp.95-96)
例①メルヒェンの主人公が逃げ場のない窮地に立たされる時の感嘆の言葉として使われる
「おや,まあ!大変だ!」“Ach,Gott”(KHM 11,16,34,37,53,59,85,89)
「気の毒に!」“DaβGott erbarm”(KHM6) など…
(参考:グリムメルヒェンのモティーフを探る ⑼―グリムメルヒェンにおける神々とキリスト教の神―満足 忍 p96)
例②魔女や小人など,主人公の行く手を阻む悪い者の発する言葉としても使われる
「12人の兄弟」(KHM9),「ちしゃ」(KHM 12)「3枚の蛇の葉」(KHM 16)で「雪白とバラ紅」(KHM 161)「いばらの中のユダヤ人」(KHM 110)
など…(もっと詳細は参考論文へ)
(参考:グリムメルヒェンのモティーフを探る ⑼―グリムメルヒェンにおける神々とキリスト教の神―満足 忍 p96)
例③「名付け親になった死神」(KHM 44)の地の文に現れるウィルヘルムのキリスト教志向
貧しい男が 13番目の子供の名付け親を求め歩く。
最初に出会った男が神であることを知ると,その申し出を「あなたを名付け親に頼むのはやめましょう。あなたは金持ちには沢山の物をおやりで,貧乏な者はひもじい目におあわせになる」と拒否し,2番目に出会った悪魔の申し出も「あなたは人を騙したり,悪いことに引き込んだりするから」と拒み、3番目に出会った死神には「あなたは申し分のない人です。あなたは貧乏人も金持ちも区別せずに連れていきます」と言って申し出を受ける。
これが、第2版では最初に出会った神の申し出を拒否する言葉の後に「この男がこんなことを言ったのも,神様がどんなに賢く,人々に富と貧しさとを振り当てておられるかを,知らなかったからです」の注釈文が書き加えられている。
(参考:グリムメルヒェンのモティーフを探る ⑼―グリムメルヒェンにおける神々とキリスト教の神―満足 忍 pp.96-97)
当コラムライターによる雑な感想:例①例②あたりのくだりは「いや、こんなん慣用句としてでしょ…」と思ったけど、そうじゃないらしい(満足,2008,p.96)。
当コラムライターによる雑な感想:例③については、「神の正当化を目的としたこの加筆はいかにも説明的であ
り,話の進展を重視するメルヒェン特性の形態からすれば不必要であると思われる。」(満足,2008年,p.97)と書いているが、キリスト教徒とは言え現代日本人である私も、まあ、そう感じる部分もある。
ただし、日本の民話(昔話)においても,こういった『語り手の意識が出る言葉』についてはそのまま記録されている場合も少なくないし、民話愛好者などはそれも大事な要素だとみなしている様子もある。ウィルヘルムのこのくだりを批判するなら日本民話におけるこういった部分も批判していかなくてはならないし、ウィルヘルムのこのくだりを批判しないなら、日本民話を読む際も同じようなスタンスをとるべきだと思うし、とらないならとらない理由を自身で定めておく必要があるだろうな、と思っている。
グリム弟自身が言った「キリスト教的」な童話
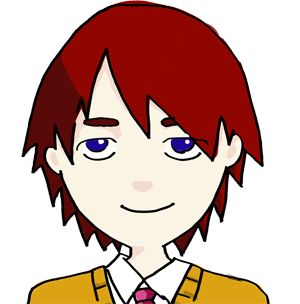
ウィルヘルム・グリム(グリム弟)は 1819年の「メルヒェンの本質について」の論文の中で『メルヒェンが極めてキリスト教的であると主張していて,その例として次のようなお話を挙げているそうです。(参考:満足,2008年,p.99)
- 「マリアの子ども」(KHM3)
- 「歌う骨」(KHM 28)
- 「手なし娘」(KHM 31)
- 「なでしこ」(KHM 76)
- 「悪魔の緑の上着」(KHM 101)
- 「明るいお天道様が明るみに出す」(KHM 115)
- 「星の銀貨」(KHM 153)
「エフタの娘」モティーフのあるグリム童話3選
士師記第 11章に収められているエフタの物語に見られる「我が子を生け贄に捧げる」モティーフである。このモティーフの本質は変化することなく伝承され,以降,多くのメルヒェンの導入部に再現され,重要なメルヒェンモティーフの1つとして根付いている。妾腹ゆえに異母兄弟から相続権を奪われ国外追放された主人公のエフタは,後になってアンモン人への戦いを指揮するために同郷の人達に呼び戻される。エフタは大事な戦いに臨むにあたり,神に「もしあなたがアンモンの人々を私の手に渡されるならば,私がアンモンの人々に勝って帰るときに,私の家の戸口から出てきて,私を迎えるものはだれでも主のものとし,その者を 祭として捧げましょう」と誓願を立てる。戦いに勝利して家に戻ると,1人娘が家から出て鼓を持って舞を踊って彼を迎える。「父よ,あなたは主に誓われたのですから,主があなたの敵アンモンの人々に報復された今,あなたが言われたとおりに私にしてください」と娘は父親の神への誓願に従って本当に生け贄に捧げられて死ぬ。彼岸の者と取り交わした約束に従って自分の子供を生け贄として捧げるこのモティーフはメルヒェンにも多く見受けられる。
(グリムメルヒェンのモティーフを探る ⑼―グリムメルヒェンにおける神々とキリスト教の神―満足 忍 p.102)
…として、この構造がある物語たちとして次の話を挙げる。
- 「手無し娘」(KHM 31)
- 「金の山の王様」(KHM 92)
- 「歌って跳ねる雲雀」(KHM 227)
当コラムライターによる雑な感想:「エフタの娘」の民間伝承との共鳴に関しては、栗林輝夫「日本民話の神学」にても言及があり、栗林自身はこれを『人柱になる娘(人)』や『蛇婿入り(水乞型/蛙報恩型?)』に見出していく論を展開している(栗林が言っているのは日本民話の話である。念のため)。私自身、キリスト教が(その是非はどうあれ)贖罪論ありきでやってきた宗教であると認識していたせいか、人身御供的な物語についてアンテナが立ってしまうことがあり、おそらくそのせいで「蛇婿入り」系のお話に執着していたので、「エフタの娘」モチーフには反応してしまう。この要素があるグリム童話については、まだ「手なし娘」しか読んだことがないので、追ってちゃんと読んでみたいと思う。
「灰かぶり」あらすじ・聖書/キリスト教要素との共鳴
あるお金持ちの妻が、病によって自分の死期を悟った。妻は小さな一人娘に
「いつまでも神様を信じて素直な心でいるんですよ。神様はいつもあなたそばについていてくださるからね。お母さんもお前天国から見守っていて、お前のそばを離れませんよ」
と言い含めた。それからこの世を去った。
女の子は毎日母親の墓へ行っては泣いていた。
やがて冬を超え春になると、金持ちの家には新しい妻がやってきた。
今度の妻は自分の娘を2人連れてきた。
この娘たちは、顔は綺麗であったが、心の中はひねくれていて真っ黒であり、義理の妹になる娘を嘲笑ったりいびるようになった。
それからと言うもの女の子は、古い服を着せらら、木の靴を履かされ、毎日毎日仕事を言いつけられる日々がかはじまった。
1日中働いた後で、どんなにくたびれていても、晩には寝床に入らず、暖炉そばの灰の中に横にならなければならなかったので、継母や娘たちは女の子のことを「灰かぶり」と呼ぶようになった。
ある日、父親が市へ出かけるにあたって、娘たちにお土産は何がいいかを尋ねた。上の2人は、きれいな着物や宝石を要求し、灰かぶりは「お父さんが帰っていらっしゃる時、1番先にお父さんの帽子に触った木の小枝を持ってきてちょうだい」と言った。
そして、行って戻ってきた金持ちは、めいめい娘たちがほしがったものを欲しがったものをやった。父親が持って帰ったハシバミの小枝を持った灰かぶりは、自分の母親のお墓のところへ行き、その小枝を母の墓にの上に置いて、泣いた。
すると、こぼれ落ちた涙が小枝に降りかかり、小枝は大きな木に成長した。
灰かぶりは毎日3度その木の下行っては泣きながらお祈りをした。
するとそのたびに1番の白い小鳥が、その木に飛んできては灰かぶりの欲しいものを何でも落としてくれた。
さて、この国の王様が、王子の花嫁になる人を探し出そうと、大きな宴会を催すことを考えたた。
それを知った継母とその娘たちは、灰かぶりを呼びつけて、自分たちの支度をさせた。灰かぶりも行きたいことを伝えると、継母は
「灰の中にお皿いっぱい分のお豆がぶちまけてあるから、それを2時間のうちに拾いなさい。そしたら一緒に連れて行ってやるわ」と
言った。
灰かぶりは裏庭から鳥を呼び、豆の選別を手伝ってもらい、継母の提示した課題をこなした。
しはし継母は、灰かぶりには着物もないし踊りもできないことを理由に、
「それじゃあ1時間のうちに灰の中から豆を2つのお皿いっぱいに拾い出せたら、一緒に連れて行ってやるよ」と言った。
これをあと2回、制限時間を短くしながら繰り返す。
しかしそのたびに灰かぶりは鳥を呼び、継母の課題をこなしてみせた。
しかし、母親は
それでも母親はやはり連れて行ってくれず、2人を連れの娘を連れてさっさと行ってしまいました,ま
家に誰もいなくなると、灰かぶりは母親の墓のところにあるハシバミの木の下に行って大きな声で呼びかけた。
するといつもの鳥が美しい着物と履き物を用意してくれた。灰かぶりさ大急ぎで着物を着替えて宴会へ出かけていった。
宴会場では、金の着物を着た灰かぶりは非常に美しく見えたので、継母にも娘たちにも気づかれなかった。
灰かぶりを一目見て気に入った王子は、早速その手を取って一緒に踊り始め、他の人とは踊ろうとしなかった。
日が暮れ、帰ろうとする灰かぶりを、王子は家まで送ってあげようと言った。
家の近くまできた灰かぶりは王子のそばをすり抜けて鳩小屋へ飛び込んだ。
王子が外で待っていると、やがて灰かぶりの父親が出てきたので、
今ここに飛び込んだ娘のことをたずねた。
父親は、(今入った娘なら、それは灰かぶりのはずだが」と思った。
そこで父は鳩小屋をまっぷたつに叩きわってみせたが、中には誰もいなかった。
それから家の中へみんなが入ってくると、灰かぶりは、いつもの汚れた着物を着て、灰の中に寝転んでいた。
(灰かぶりは、鳩小屋の後ろから飛び出して、着物を脱いで、お墓の上に置いて、いつもの場所で眠っていたのである。着物は鶏がどこかへ持っていってしまった。)
その次の日もまた宴会が催されたので、灰かぶりは昨日と同じように宴会に出た。
この日は、王子は灰かぶりがどこに帰るのか突き止めようとあとをつけた。
しかし、灰かぶりは庭の木にに飛び込んだので、王子は見失ってしまう。
3回目も同じようなことを繰り返す。この日も日が暮れたので灰かぶりは帰ろうとしたが、この日は王子は計略をを巡らしていて、階段中にベタベタする薬を塗らせていた。
なので灰かぶりは、左の上靴を階段に残していくことになった。
王子がその靴を取り上げてみると、それはちっちゃくて全部金でできていた。
その次の朝王子はその靴を持って金持ちの男のところへ行き「この金の靴がぴったり、足に合う女を、僕は妻にしたいのだ」と言った。継母はまず上の娘に靴を履かせたが、入らなかったので、包丁渡して「靴足の指なんか切ってしまいなさいよ。お妃になれば、もう足で歩くこともないからね」と言った。
そして指を切った上の娘は痛いのを我慢して部屋を出て王子のところへ行き、それで王子はこの娘を馬に乗せ、城に戻ろうとした。
ところが、墓のハシバミの木のそばをとおると、橋の木に止まっていた庭の鳩が
ちょいと後ろを見てごらん
ちょいと後ろ見てごらん
くつのなかは血がいっぱい
だってくつがちいちゃすぎるもの
ほんとのよめさん うちにいる
と呼びかけた。
王子は引き返して偽の花嫁を
次は下の娘がかかとを切り落とて、同じように王子の馬に乗ったが、またもやハシバミの木のそば。通ったときに、庭の鳩があのような歌を歌った。
王子はまた引き返しもう他に娘がいないかと問い詰めたので、父親が
「もっとも、亡くなりました家内が残していた娘が1人おりますが、これは発育も遅れておりまして、いつも灰だらけの汚い格好しております。とても花嫁になれるようなものではございません」と答えた。
王子はそれでも構わないから、と言って灰かぶりを連れて来させた。
灰かぶりは、まず両手と顔をきれいに洗い、それから出てきて、王子の前でお辞儀をした。そして靴を灰かぶりに履かせると、ぴったりと灰かぶりの足にあった。
灰かぶりを馬に乗せて王子が出かけ、
ハシバミの木のそばを通り掛かると、鳥たちが
ちょいと後ろを見てごらん
ちょいと後ろを見てごらん
靴の中に血はないよ
靴はちいちゃすぎないもの
今度は本当の花嫁連れて行く
と歌い、舞い降りて灰かぶりの肩の上にそれぞれとまった。
いよいよ、灰かぶりと王子の婚礼が行われることになった時。偽の花嫁を騙った2人の姉妹は、灰かぶりの幸せを分けてもらおうと思いやってきた。
すると、2羽の鳩が飛んできて、姉妹の目玉を1つずつつつきだした。最終的ににはそれぞれ両目ともつつき出されて、一生目が見えなくなった。
(参考:矢崎源九郎訳「灰かぶり」)
聖書との共鳴:ハシバミの枝

主人公が母親の墓に植えた「ハシバミの若枝」が、ドイツ語圏における創世記ヤコブの物語にみられる描写からではないか研究者は考えている。(参考:堀川敏寛,2022年)
実はこの「ハシバミの若枝」という描写は初版にはなく、この枝が「ハシバミ」であると描写されるのは第二版以降なのだそうだ(野口芳子2016,71)。つまり“主人公が母親の墓に植えた植物はハシバミ”という描写はヴィルヘルム・グリムがあとから意識的に付け足した部位であると考えていいようである。
意識的に付け足すということは、グリムたちを取り巻いていた習俗に何か謂れがあるのではないか…ということで、野口芳子氏は以下のように述べる。
グリム兄弟の『ドイツ語辞典』(Deuchetes Worterbuch)によると、「若枝は法律の象徴」であり、渡された若枝を土(Scholle)に埋めるということは、慣習法では遺産の譲渡と相続の完了を意味する。また、ヤーコプ・グリムの『ドイツ神話学』()Deutsche Mythologie)によると、ハシバミの若枝は「魔法の枝」として用いられ、それは、「宝物をもたらしただけでなく、姿形をより一層優れたものにしてくれる」そうだ。(中略)
ハシバミの若枝は古代から‛Wunschelruthe’として呪力や魔力を持った存在、つまり「魔法の枝」。「占い棒」、「金の枝」として民衆に親しまれていたのである。(野口pp.70-71)
そのうえで、堀川氏は、創世記30章のヤコブの物語に登場する植物がドイツではハシバミとみなされていたのではないか…みたいな話をする。
ヤコブは、はこやなぎと、あめんどうと、すずかけの木のなまの枝を取り、皮をはいでそれに白い筋をつくり、枝の白い所を表わし、 皮をはいだ枝を、…(創世記30章37節)
…と、(黄色線)現代日本語で聖書を読むことに慣れた方々にとっては、ここは“アーモンドじゃないか!と思われるのではないかと想像するが、グリム辞典によると、こういった訳がなされていたそうで、
そこでヤコブは、緑のポプラの木、ハシバミを取って、白い縞模様になるよう、その皮を剥いだ。
“Jacob aber nam stebe von grünen papelnbawm, haseln, und castpneen,und Schelte weisze streife daran (1 Mos. 30, 37),” (Deutsches Wörterbuch: Bd. 10, S. 530).
これは、ヤコブが羊や山羊などの家畜を繁殖させるため、ある種の魔術を駆使した場面である。
(中略)
として、ヴィルヘルムがこの辞典を参照して「ハシバミの木の枝」という描写にしたのではないか、と堀川氏は述べる。()
▽創世記(後半)の全体像
このような木の枝を使った魔術の他にも、ヤコブ物語の創世記28:18のなかで一神教崇拝らしからぬ行いを確認することができる。そこでは神がヤコブの夢のなかで顕現したあと、ヤコブは枕にしていた石を取って石柱を作
り、そこに油を注ぐという、土着の慣習的儀礼を行なっている。これは聖書のなかに見られる、その土地の慣習の名残であろう。ちなみにヘブライ語聖書では、本来、魔術や呪術は、土着の「異教」が執り行っている儀礼の一形態として、律法のなかで厳格に禁じられている。申命記18:10-12やエレミヤ書27:9では、呪術師が神によって忌み嫌われる存在であり、あってはならない、と戒められる10。ところが同時に、ヘブライ語聖書では、造られた青銅の蛇を竿の上に掲げることで蛇に咬まれた人の命を救ったモーセ(民数記21:8-9)、口寄せ(霊媒師)の女を訪れて死者サムエルの霊を召喚するよう頼んだサウル(サムエル記上28:8)など、聖書で禁じられているにもかかわらず、魔術や霊媒に頼る登場人物たちが存在している。それは聖書全体が一枚岩で筋のとおった書物ではなく、複数の解釈が可能であるばかりか、相反する理解が共存する書であるからである。
(引用:「グリム童話に見られる聖書的モティーフ─上方と下方という観点から」堀川敏寛,2022年,p.83-84)
当コラムライターによる雑な感想:ヘーゼルナッツ(ハシバミの実)が使用されている食品で現代日本で有名なものといえば『ヌテラ』なのではないかと思うが、これはとりわけ、ドイツ人がめちゃくちゃ好きらしい。(ヌテラ自体はイタリアのフェレロ社という会社の商品)。ヌテラがヘーゼルナッツのクリームであることを知って、ヘーゼルナッツと聖書の関係について調べたことがあったのだが、現代日本語聖書や現代日本のインターネットをさらうだけでは「ヘーゼルナッツはヨーロッパでめちゃくちゃ愛されているにも関わらず、聖書には登場しないナッツである」としか思えなかった。甘かった。ヌテラより甘かった。グリムたちが見ていた聖書の世界にはヘーゼルが存在していたのだ。現代日本人として聖書を読む人間の感覚でしかなかったのだと思わされた。(グリム童話にもハシバミが広く愛されるようになった植物起源伝説として「ハシバミの枝」という物語があるので、『昔話(民話)としてはあるのねぇ…』くらいに思っていた)世界は広く、沼は深い。私は何も知らない人間なのだと感じる。ヌテラでも食べて生きていこうと思う。
当コラムライターによる雑な感想②:宗教改革者であるマルティン・ルターの伝説にこんなものがあるが、ポルターガイストに悩まされる(?)ルターの話にヘーゼルナッツが登場するのは、やっぱりハシバミという植物を魔除け的なものとみなす習俗があったことを思わせる感じがあって、興味深い。
「ラプンツェル」あらすじ・聖書/キリスト教要素との共鳴

昔々、あるところに、子どもをなかなか授からない夫婦がいた。
2人の家の窓からは、とてもきれいな花や薬草のたくさん生えている庭が見えていた。
その庭は、みんなから怖がられている魔法使いの女のもので、高い塀に囲まれており、誰も中に入ろうとするものはいなかった。
ある日、妻がその庭に生えているラプンツェルを見かけて、それがどうしても食べたくなった。
妻の異変に気づいた夫が事情を尋ねると、妻は「家の裏手に生えているラプンツェルが食べられないと、私は死んでしまうわ」と言うので、夫はあのラプンツェルをとってくること決意した。
あたりが暗くなってから庭に侵入して、ラプンツェルを1つ上抜き取って持って帰ることに成功した。
妻はそれをサラダにしてガツガツたいらげた。
しかし、妻は次の日には3倍も食べたいと訴え、夫は仕方なくもう一度裏庭へ忍び込んだ。
しかし今度は魔法使いの女に見つかってしまった。攻め立てられた夫は事情を話した。
それを聞いて、魔法使いは怒りを和らげ「そういうわけなら、ラプンツェルを好きなだけ持たせてあげよう。だが、それには1つ条件がある。女将さんが子供を産んだら、お前はその子を私に汚さなくてはいけない。子供は幸せにしてやるよ」夫は何もかも承知した。
そして妻は懐妊し、やがて出産した。
すると、魔法使いがやってきて、子供にラプンツェルという名前をつけ、連れさってしまつた。
ラプンツェルは12歳になり、美しい子に成長した。魔法使いの女はラプンツェルを、森の中にある、出入り口も階段もない、窓がひとつの塔に閉じ込めた。
魔法使いが「ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ」と叫ぶと、ラプンツェルが長い髪を下に垂らして、魔法使いはそれを使って塔に登った。
それから2-3年たったころ。この国の王子が、馬でラプンツェルの住む塔のそばを通りかかった。
そこで美しい歌声を聴いた王子は、声が塔からすることに気づき、登ろうと試みる。
木の影に隠れていると、魔法使い女が塔から降ろされた髪の毛につかまって登っているのを見たので、王子は魔法使いが塔から離れたのを確認し、見よう見真似で魔女と同じように叫んだ。
そして王子は塔に登ることに成功した。
ラプンツェルは初めて見る男性にひどくおどろいたが、王子が優しく話すので、やがて『この人は、ゴーテル(名付け親の意)のおばあさんより私を愛してくれるだろう』と思うようになった。
そして「あなたがここへ来る時、そのたびごとに絹糸を1巻持ってきてください。それではしごを編みます。それで下に降りたら、あなたの馬に乗せてください」と、逃亡の計画を話した。
そして王子は毎晩ラプンツェルのところに来るようになった。
魔法使いの女はしばらく何も気づかなかったが、ある時、ラプンツェルはうっかり「なぜおばあさんを引っ張り上げる方が重いのかしら」と口を滑らしてしまう。
魔法使いは怒り、ラプンツェルの美しい髪を切り落としてしまった。
そしてラプンツェルは荒れ野へ追放され、惨めな暮らしをはじめることになった。
ラプンツェルが追い出されたその夜、何も知らない王子はいつものように塔にやってきて、声を上げた。魔法使いはラプンツェルの髪を垂らし、王子をそのまま上って来させてラプンツェルはもうここにはいないことを告げた。
王子は心の痛みに耐えかね、捨てばちな気持ちで塔から飛び降りた。命は助かったが、茨の中に落ちたので、両目が潰れてしまった。
それから王子は目の見えないまま森の中を、何年もさまよい歩くことになった。
数年さまよっていると、王子はやがてラプンツェルのいる荒野へやってきた。
ラプンツェルは双子の男の子と女の子を出産しており、3人で暮らしていた。
王子は聞き覚えのある声を聞き、ラプンツェルと再会する。
ラプンツェルは王子に気づき、首にすがりついて泣いた。
その涙が2つ分王子の目の濡らすと王子の目はまたはっきりして元通り見えるようになった。
王子はラプンツェルを自分の国へ連れて行って大喜びで迎え入れられた。そして2人はそれからずっと楽しく幸せに暮らした。
(参考:「決定版 完訳 グリム童話集 1」野村泫 訳,pp.124-134,1999年,筑摩書房)当コラムライターによる要約
聖書との共鳴:荒野への追放・罪の遺伝

・荒野への追放
・罪の遺伝
という要素が、極めて聖書的モティーフである。(参考:堀川,2022年,pp.85-86)
ヘブライ語聖書の創世神話では、エデンの園からの追放(3章)後、4章から兄弟殺しを主題とする「カインとアベル」の物語が始まる。この物語のなかで、カインは弟を殺害するのだが、それに応じた罰として、神はカインをその地から追放する(創世記4:11)。このようにラプンツェルと王子に起こった荒野への追放というプロットは、極めて聖書的モティーフである。アダムとエヴァのみならず、その息子カインも、殺人の罪にたいする罰として追放されているのだ。そしてこれが聖書神学のテーマ「罪の遺伝」である。それはヘブライ語聖書の原罪理解につながり、最初の人類であるアダムが犯した罪が、その後の子孫へと遺伝していくことである。 「ラプンツェル」では、まさに両親が犯した盗みという罪が、娘に遺伝し、禁じられていた男性との密会と妊娠という罪をラプンツェルも犯すのである。それにたいして物語では、親と子にたいして、それぞれ罰が与えられている。このように「ラプンツェル」は、楽園追放のみならず聖書物語で繰り返し行われる人類の過ちに関して、「罪の遺伝」という神学テーマに沿ったプロットを採っていると、筆者は考える。ちなみにこの罪の遺伝とは、未来永劫つづくものではない。それはキリストによる救済もしくは王子との再会によって終焉する。この事態をパウロは、ローマの信徒への手紙5:19のなかで「アダムに死に、キリストに生きる」という表現によって説明している。
(引用:「グリム童話に見られる聖書的モティーフ─上方と下方という観点から」堀川敏寛,2022年,p.86)
 ディズニー作品における「異類婚姻譚」の例5選~リトル・マーメイド/美女と野獣/プリンセスと魔法のキス等~
ディズニー作品における「異類婚姻譚」の例5選~リトル・マーメイド/美女と野獣/プリンセスと魔法のキス等~
↑正確に言うとこの記事では取り扱っていない。取り扱おうとしてやめた言及が残っている。
ライターによる雑な感想:聖書の内容を知らなかった時代に読んだラプンツェルの物語は、若かったということもあるだろうけれど、夫妻・ラプンツェルともどもが後ろ暗いことをしているのにハッピーエンドになる…みたいな着地がんまり得心できなくて、けっこう『後ろ暗い物語』という印象でしかなかった。成人してもはや中年にさしかかり、聖書内容にもそれなりになじみがでてきた現在、こういった視点で読むと、なるほど、『登場人物たちが後ろ暗いからこそ見える景色があるのか』という感じである。聖書を読み通していくさいに嫌になるほど繰り返される人間の過ちに比べると、2代で終わる話なので相対的にストレスも低く読みやすい(あたりまえ体操)
ライターによる雑な感想②:この解釈を踏まえてこの物語を読むと、現状のライター的には「ラプンツェル」がグリム童話で1番好きかもしれない。
「貧乏人と金持ち」あらすじ・聖書/キリスト教要素との共鳴
むかしむかし、まだ神さまがご自身で人間の世界を歩き回っていたころのおはなし。
神さまは、日が暮れてきたので、どこかの家に泊めてもらおうと思った。
行く手には2件の家が向かい合って建っており、一軒は大きくて、もう一軒はみすぼらしかった。
「金持ちなら迷惑にはなるまい」と考えた神さまは、大きな家にひと晩の宿泊を乞うた。しかし金持ちは「泊めてあげられないんだ。部屋という部屋に、薬草や種子がいっぱいつまっているのでね。」
などど言って断った。
次に神さまは、向いの貧しい家にひと晩の宿を求めた。貧しい家の住人は快く歓待した。
貧乏人のおかみさんはじゃがいもを火にかけ、いもが煮えるあいだにやぎの乳をしぼり、せいいっぱい旅人(神)をもてなした。
そして、自分たちはわらを敷いて寝て、旅人にはベッドを使ってもらうように相談しあって、そのようにした。(神も固辞したが、貧乏人夫婦がどうしても勧めるので受け入れた)
翌朝にも、せいいっぱいの朝食でもてなされた。神は出発のときになると、敷居のところに立って
「あなたがたはたいそう思いやりがあり、とても信心深いので、わたしが願いをかあねてあげよう」と言って、願いを3つ聞き出した。
貧乏人は
「何よりもまず、死んだら天国へ行きたいと思います。
それから、どうにか暮らしていけるだけの食べ物が毎日ありますように、3つ目は、何を願ったらいいのか思いつきません」
と言った。神は、古い家を新しくしなくはないか?たずね、貧乏人はありがたく受け入れた。古い家は新しい家に変わり、神はふたりに祝福を与えて立ち去った。
昼間、金持ちが向かいの家を見ると、いきなり新しく立派な家が建っていたので、おどろき、妻を呼び、ことの次第を向かいに確かめに行くことにした。
そして、金持ち夫妻は、昨日自分たちが断った旅人の力でこのようになったことを知って後悔した。
追いかけて自分たちの望みもかなえてもらおうと思い、亭主が馬に乗って神の後を追いかけた。
金持ち亭主は神に愛想よくはなしかけ、「次にやってくることがあったら自分たちの家に泊まってください」と言った。その際には3つ願いをかなえてください、とも言い、神はそれを承諾した。
金持ち亭主は機嫌よく帰路についたが、道中。どうにも馬が言うことを聞かないので「おまえなんぞ、首の骨を折ってしまうがいい」と言った。その瞬間、馬は倒れてうごかなくなった。
金持ち亭主は、しかし願いはまだ2つ残っていると思い、馬からくらをとりはずして担ぎ、次の願いを何にするかをひたすら考えながら歩いた。考えるうちに、家では自分の妻が気楽にうまいものでも食べて待っているのではないかと想像し、「女房なんて、うちでくらに乗ったままおりられなくなってしまえばいい」と口走った。
その瞬間、金持ちは自分が背負っていた鞍が消えたことに気づき、2つ目の願いも叶えられたことを悟った。
金持ちはかっとなり走りだして、自分の部屋にもどってひとりで一番良い願いを考えだそうと思った。しかし家にもどってみると、やはり自分の妻がくらに乗ったまま泣きわめいていた。
妻は「くらに乗ったきりなら、世界中の宝をもらったって何の役にも立ちやしない」と言い、自分をおろすように要求してきたので、金持ちはそれを聞き入れざるをえなかった。
そういうわけで金持ちは、腹を立て、無駄骨を折り、ののしられ、馬を死なせたのであり、
貧乏人夫婦は、楽しく、穏やかに、信心深く暮らし、しまいに安らかに息を引き取った。
(参考:「決定版 完訳 グリム童話集 4」野村泫 訳,pp.99-107,1999年,筑摩書房)当コラムライターによる要約
聖書との共鳴:ソドムとゴモラ

この話のプロットは、創世記19章の「ソドムとゴモラの滅亡に関するロト物語」
と同じである。(堀川,p.82)
ない…。取り扱いたいとは思いながらそこまで手が回ってない。
LampMateチャンネルの「世界のお菓子と世界の民話」シリーズでならちょいちょい言及していきたいという気持ちならある。
当コラムライターによる雑な感想:「神がマレビト的な感じで人間の世界を遊行する」という民話はヨーロッパにめちゃくちゃあり、日本にもめちゃくちゃある。日本の場合、弘法大師・空海が一番多いのではないかと感じるが、行基も多いらしい。そしてこの物語で言うと、「蘇民将来」として知られているお話と似ている話である。
つまり蘇民将来には創世記19章あたりのプロットと共鳴しているということかぁ…。と考えると、民間説話の世界の沼の深さにめまいがしそう。
「ヨリンデとヨリンゲル」あらすじ・聖書/キリスト教要素との共鳴
昔々、大きな森の真ん中にある古い城に、魔法使いの老婆が住んでいた。この老婆は、昼の間は猫になったりフクロウになったりして、鳥を引き寄せ殺し、煮たり焼いたりしていた。
また、城に近づく人間はその場から動けなくすることもできた。
汚れのない娘がその区域に入ってくると、老婆はその娘を鳥に変えてカゴに閉じ込めた。
そうして鳥を閉じ込めたカゴを、城に7000ほど持っていた。
さていつの頃か、ヨリンデと言うとても美しい娘がいた。
この娘にはヨリンゲルと言う婚約者がいて、2人はお互いが本当に好きで好きでたまらなかった。
ある日、2人は、愛を語り合いたいと思って、森へ散歩にやってきた。
しかし、愛を語らうふたりは森で迷ってしまう。
日が暮れそうで焦った2人は城に近づきすぎてしまい、ヨリンデはナイチンゲールに変わってしまった。
そこへフクロウが飛んできて、老婆の姿になってナイチンゲールを捕まえた。
ヨリンデル身動きできずことの成り行きを見ていることしかできなかった。
ナイチンゲールを手に乗せた老婆は、向こうへ運んでいき、また戻ってきて「こんばんは、ザヒールや。鳥にお月様が差してきたら話してをやり。良い頃合いにね」と言った。
するとヨリンゲルは体を動かせるようになったので、ヨリンデを返してくださいと懇願した。
しかし老婆は返してやるものかと言って言ってしまった。
ヨリンゲルは泣き叫んだがどうすることもできないので、そのまま住んでいるところを離れ、さまよい歩き知らない村やってきた。
そしてその村で長いこと羊の番を押していた。
そうやって暮らしているうちにヨリンゲルは夢を見る。
ヨリンゲルの夢の内容…
ヨリンゲルは、真ん中に大つぶの真珠がついた血のように赤い花を見つけ、それを折りとる。
それを持って城に行くと、その花で触ったものは何もかも魔法が解けた。
そして愛しいヨリンデを取り戻す。
目が覚めたヨリンゲルは、その花を見つけるため、山や谷を探し始めた。
そして、とうとう夢で見たような赤い花を見つけた。
ヨリンゲルはその花を持って城へ向かった。
城へ近寄っても体が動かなくなる事はなく、そのまま門をくぐり、中庭を通り、広場まで来ると、そこには魔法使いがいて、7000のカゴに入った鳥たちに餌をやっていた。
魔法使いはヨリンゲルを見ると、腹を立てて怒鳴りつけ毒や胆汁を吐きかけてきた。
しかし、魔女はヨリンゲルの2歩手前までしか近づけないようであった。
ヨリンゲルは老婆には目もくれず、広間を歩いてナイチンゲールを探した。しかし、そこにはナイチンゲールが何百羽といたので、4人でが何どれであるのかわからなかった。
籠を見て回っているうちに、老婆が鳥の入った籠を1つ持ち出して外の方へ向かっていくのが見えたのヨヨリンゲルは、老婆に近寄り、花で籠と老婆にそれぞれ触った。
すると老婆は魔法の力を失ったようで、たちまちヨリンデは姿を取り戻し、ヨリンゲルを抱きしめた。
ヨリンデの美しさは少しも変わっていなかった。
それからヨリンゲルは他の鳥たちもみんな娘に戻してやり、2人はともに家へ帰り、末永く長い間楽しく一緒に暮らした。
(参考:「決定版 完訳 グリム童話集 3」野村泫 訳,pp.227-232,1999年,筑摩書房)
聖書との共鳴:ギデオンの露の奇蹟
この露の玉を、ビルクホイザー−オエリは、ヘブライ語聖書の士師記で描写された「ギデオンの露の奇跡」から採られたアイデアである、と推測している…らしい(堀川,)
「伐採者」という意味。士師記6章11節~8章32節で言及。
ギデオンは神に言った。「…私は羊一匹分の毛を麦打ち場に置きます。もしその羊の毛にだけ露が降りて、地面が乾いているのであれば、お告げになったように、私の手によってイスラエルを救われるということを納得いたします」。(士師記6:36-37)
ライターによる雑な感想:このコラムを書くにあたって初めて知ったお話。普通に読むと「特に面白いとは思えない話」だったが、こういうモチーフにこういう意味があるのだと思いつつ見返すと非常に感慨深い……。“この物語をあらすじ要約しろ”と言われたら省いてしまいそうな部分に、神話的な要素があり、それを読みといていくとこんな景色が見えるのかぁ……と感動したと同時に、じゃあ自分が日本昔話なんか読むときも色々見落としているものがあるんだろうな…と思わされ、怖さも感じた。
いまのところナシ…?
日本で一番有名な「ギデオン」は聖書を無料配布している「一般財団法人日本国際ギデオン協会」か、ピノキオに登場するジョンの相棒ネコですかね…
(途中)「忠実なヨハネス」あらすじ・聖書/キリスト教要素との共鳴
金成陽一がこれについてまるまる一冊本を書いている。
聖書との共鳴:
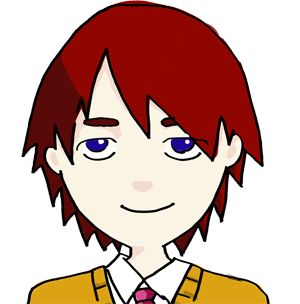
「忠実なヨハネス」には『ヨハネ』(洗礼者ヨハネ,使徒ヨハネ)の面影を見ることができるのではないか
もう少し色々文化的な背景を挟むと…
「かえるの王子様」に潜む、当時のキリスト教社会の影響っぽい『グリムの理想の女性像』
親に従順で何でも命令どおりに行動していた娘が、初めて自己主張をし、親に従属していた子供としての自分を殺し、本当の自分を自覚した大人としての自分を生み出したのである。親という色眼鏡を通して見ていた時には、蛙のようにいやらしい人に見えたが、先入観を取り外して自分自身の眼で見ると、王子のように美しい人であることが分かった。()主体的に自分の行動を決定したこの王女は、自立した女性であり、このメルヒェンは女性の解放を目指した文学の一種であるともいえる、というのが彼(レレケ)の解釈である。
(野口,88)
↓
野口はこれを否定。
即ち、この女王は、たとえ父親の命令であろうと、意に添わない相手、まして結婚もしてない相手と交渉を持つことを明確に拒否し、自分の純潔を守り通したのである。その彼女の堅い操が幸福な結末を勝ち取ったのである。というように解釈する方が時代を考慮に入れると的を射たもののように思われる。
として、その理由というのが、当時のヨーロッパのキリスト教社会では、誘惑にあらがって自分の操を守り通せる女性が人々の鑑だと考えられていたであろうこと、グリムたちのストイックさと、彼らが「自分たちの理想とする女性像を見た」と考えるほいが自然であるという考えを述べている(p.89)
当コラムライターによる雑な感想:「時代と地域を定義せずにキリスト教の話はできない」というが、こういうのを読むとやっぱりそうだなと思う。(論考じゃなくて草)
『ヘンゼル』『ハンス』の響きは元をたどれば「ヨハネ(ジョン)」。だが…
「ヨーロッパにおいて、記録されている限りではもっとも量の多い民話」こと『クマの子ジャン』の『ジャン』はそれこそ「ヨハネ」由来ではあるが、その実、『それは聖書のヨハネではなくてその奥にケルトの原始信仰の信仰対象がいるんだなぁ』と言っていた書籍の記憶がうっすらある(たぶんフィリップ・ヴァルテールの「中世の祝祭」だと思う)
また調べられたら補足したい(希望)
当コラムライターによる雑な感想:以前の自分なら『キリスト教以前の信仰だからキリスト教由来じゃないのかあ…(残念)』みたいに思っていたかもしれないけれど、今となっては、それらの上にキリスト教が咲いて、さらに混交・変化・分離・分割していって今に至るわけで、現代日本人の私が三位一体の神の慰めにあずかれると思える理由そのものでもあり、慰めの根拠なのである。ゆえ、私にとっては慰め深い話である。(は?)
「グリム童話には親孝行な息子を神が褒める話は存在しない」
野口芳子氏の論文集を読んでいて気になったのはこのような箇所。
グリム童話には親不孝な息子の行動を神が罰する話は存在するのに、親孝行な息子を神が褒める話は存在しない。
野口 p.112
らしい。おもしろい。
現代の日本語圏における聖書の解釈で「親不孝な息子の行動を神が罰する」あるいは「親孝行な息子を神が褒めた」と無理なく解釈できそうなくだりあったかなぁ…ありそうだけどパっと出てこないよ…
えっ?ルンペルシュティルツヒェンは?お前まとめ記事まで作ってるじゃん
…なんて言ってくれるくらい当コラムライターと興味を一にしてくれる方がいるとは思っていないけれど、一応、こんなまとめ記事を作ってインターネットに放流している身として
 ルンペルシュティルツヒェン・トムティットトット系昔話10選あらすじ&教訓など紹介していく【小人の名前一覧マップ付】
ルンペルシュティルツヒェン・トムティットトット系昔話10選あらすじ&教訓など紹介していく【小人の名前一覧マップ付】
補足しておきたいと思う。
確かに当コラムライターは「ルンペルシュティルツヒェン」系のお話に執着している。そして筆者は「ルンペルシュティルツヒェン」から日本人がなにかエキスを得るなら『あなたの地域に生きる蛇婿入りの教訓からじゃないのか』と思っている。
ひいては、それが私のプロテスタンティズムなのだ、という考えてやっている。
これに関しては、現代日本における民間説話愛好者や、キリスト教徒側からも賛同がえられない考え方であることは栗林輝夫「日本民話の神学」をめぐるアレコレで感じている、のであまり詳しくはここでは触れない。
この件について改めて何かまとめられたらいいなとは思っている。
グリム童話じゃないドイツの民話・伝説
当チームがYouTubeチャンネルに設けている「お菓子を作りながら民間伝承を紹介していく」というコーナーがある。
チーム内で決めている方向性として「日本人のキリスト教徒が観て、おもしろいと感じてくれそうなものをチョイスすべし」という監修役からの指令と縛りがある。
制作者(当コラムライター)自身は、「キリスト教徒・非キリスト教徒関係なく『平地人が戦慄したらいいのに』」というモチベーションで民話を漁っているので、「現代日本人キリスト教徒が面白いと感じそうなもの」という縛りには反吐が出そうになる気が滅入ってしまう。
しかしどうにかやっているのは確かなので、つまりここで紹介しているものは、背景はどうあれ『おおむねキリスト教要素を見出せる民間伝承』なのではないだろうか、と思う。
……髑髏の丘で磔刑に処された男の声が聴きたくて、こんなところまで来てしまった(結びの句)……
改めて参考書籍・文献
▽これは平行して読んでるけど引用してないかも



